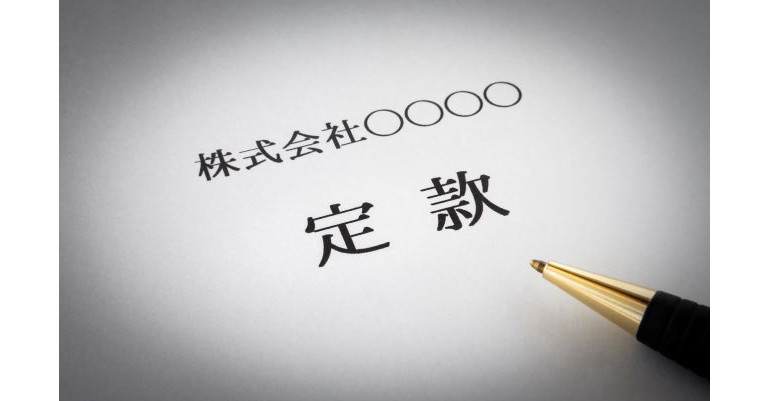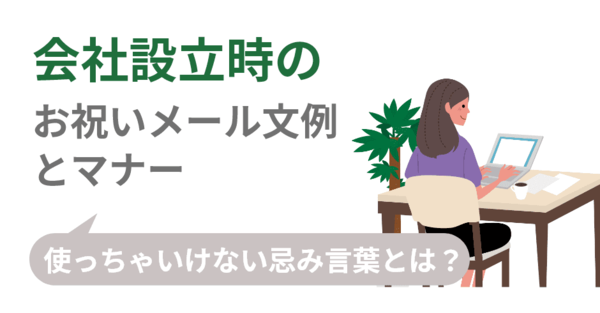会社設立と個人事業主の起業との違いは?法人化の手続きの流れも解説


個人事業主の人の中には、事業が安定してくると様々な要因から法人会社の設立を検討し始める人もいますよね。個人事業主が法人会社を設立することでどのような変化があり、その際にどのようなメリットとデメリットが生じるのか知りたい人もいるでしょう。
個人事業主が法人会社を設立して変わることとして、たとえば「費用面」と「社会的影響面」が挙げられます。節税や社会的信用に関するメリットが得られる一方、これまでに発生しなかった費用や手間がかかるなどのデメリットが生じます。
当記事では、個人事業主が会社を設立する際のメリットデメリットを解説します。法人会社を設立することで変わることやメリットデメリットを理解し、設立するタイミングの見通しを立てたい人は参考にしてみてください。
事業を始めようとしている人の中には、会社を設立するか個人事業主として起業するかで悩んでいる人もいますよね。会社設立と個人事業主として起業する違いを知りたい人もいるでしょう。
会社とは会社法に基づいて運営される組織(以下、法人)のことで、株式会社や合同会社などが該当します。一方、個人事業主は、会社を設立せずに個人で事業を営む人をさします。事業を始める際の手続きや経費の範囲など、会社設立と個人事業主としての起業では事業を運営する際のルールが異なります。
当記事では、会社設立と個人事業主との起業の違いや、個人事業主が法人化する際の手続きの流れを解説します。それぞれのメリットとデメリットも解説するので、事業を始める予定の人は参考にしてみてください。
会社設立と個人事業主の起業との違い
会社設立と個人事業主の起業では、おもに事業を運営する際のルールが異なります。事業規模の拡大や収入の増加により事業の法人化を検討している人は、法人と個人事業主にはどのような違いがあるのかを理解しておきましょう。
【会社設立と個人事業主の起業で異なる項目】
- 事業開始の手続き
- 社会的な信用
- 税金の扱い
- 経費の範囲
なお、法人と個人事業主にはそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらの事業形態が向いているのかは事業者によって異なります。各項目におけるメリットとデメリットを確認し、事業形態を選択する際の判断材料のひとつにしてみてください。
事業開始の手続きの違い
事業の手続きでは、申請時の手続きや手続き費用などが法人と個人で異なります。
【事業開始の手続きの違い】
|
事業を営む形態 |
法人 |
個人事業主 |
|
事業開始に必要な申請 |
法務局への登記申請 (定款や資本金の払込みの証明書などの添付書類も必要) |
税務署への開業届 (青色申告をしたい場合は青色申告承認申請書の提出) |
|
事業開始までの手続き費用 |
|
不要 |
|
事業年度 |
自由に設定可能 |
1/1~12/31 |
|
赤字の繰り越し可能年数 |
10年 |
3年 |
|
社会保険の加入 |
必須 |
5名以上であれば加入必須 |
個人事業主の場合は、税務署へ開業届を提出すれば起業できます。登記の申請や定款の作成は不要であり、資本金も必要がないため、原則として事業開始までの手続きにおいて費用が発生することはありません。
一方で、法人の場合は、法務局への登記申請が必要です。登記申請で提出する書類には定款や資本金の払込みの証明書などの準備が必要であり、定款の作成には専門の知識を要します。
会社設立の際は、必要に応じて行政書士や司法書士などの専門家に書類作成を依頼することもあります。登記申請の代行は司法書士にしか依頼できないため、専門家を頼る人は士業によって依頼できる作業内容を確認しておきましょう。
それぞれの士業が何の作業を担当できるか知りたい人は「会社設立において行政書士に依頼できる業務と費用を解説」を参考にしてみてください。
手続きの違いから見たメリットデメリット
法人と個人事業主では会社設立にかかる手続きが異なり、それぞれメリットとデメリットがあります。会社を設立するか個人事業主として起業するか悩んでいる人は、法人と個人事業主の手続きを比較してみましょう。
【手続きの違いから見たメリットデメリット】
|
事業形態 |
メリット |
デメリット |
|
法人 |
|
|
|
個人事業主 |
|
|
法人の場合、事業年度に決まりがなく繁忙期を避けて決算期を迎えられることや、社会保険による恩恵を受けられるなどのメリットがあります。しかし、個人事業主よりも必要な手続きが多いことや、社会保険による支出の増加などのデメリットもあります。
個人事業主の場合、起業するときにかかる手間や費用を抑えられることがメリットとなります。しかし、事業年度が1/1~12/31と決まっていることや、赤字の繰り越し可能年数が法人よりも短いことなどがデメリットとなる可能性があります。
社会的な位置づけや信用の違い
法人と個人では、社会的な位置づけや信用度も異なります。社会的な信用があることで、融資を受けやすくなる可能性があります。
【社会的な信用の違い】
|
事業を営む形態 |
法人 |
個人事業主 |
|
融資 |
有利 |
不利 |
|
責任の範囲 |
有限責任 (株式会社または合同会社の場合) |
無限責任 |
|
確定申告 |
税理士や会計士が確定申告をする場合が多い |
個人で確定申告 |
法人は、法律に基づいた運営や決算書の開示をして財務状況の報告が義務付けられていることから、取引先や金融機関から信用を得やすくなります。一方、個人事業主は、法人格がないことで社会的信用を得にくく、融資でも不利になる可能性があります。
また、倒産したときの責任範囲も違いがあります。法人の場合、出資者は自身が出資した額の負債のみ支払い、出資額を超えた分は支払いの必要がありません。一方、個人の場合はすべての負債を支払う責任が生じます。
確定申告時の手続きの場合、法人は法人税法が定める帳簿や決算書の作成をすることが求められるため、個人事業主よりも提出物が多く煩雑となる傾向にあります。一方、個人事業主は法人と比べると経理作業は簡易的です。
社会的な位置づけの違いから見たメリットデメリット
法人と個人事業主では社会的な位置づけが異なり、それぞれメリットとデメリットがあります。会社を設立するか個人事業主として起業するか悩んでいる人は、法人と個人事業主の社会的な位置づけや信用度を比較してみましょう。
【社会的な位置づけの違いによるメリットデメリット】
|
事業形態 |
メリット |
デメリット |
|
法人 |
|
|
|
個人事業主 |
|
|
法人の場合、法律に基づいて運営されていることから社会的な信用を得やすいことや、倒産時の負債の範囲が決まっていることがメリットです。しかし、決算時には決算の内容を公に告知する「決算公告」の義務が発生し、会計管理の手間がデメリットとなる可能性があります。
個人事業主の場合、確定申告時の手続きや提出物が法人と比較して少なく、負担が軽いことがメリットです。しかし、社会的な信用は法人と比較して低い傾向にあるため融資を受けにくくなるなることや、倒産時の負債をすべて支払う義務が生じることがデメリットとなる可能性があります。
税金の違い
法人と個人事業主では、所得にかかる税金も異なります。法人と個人事業主のどちらも金額によって税率が決められていますが、個人事業主は法人よりも細かく税率の区分が定められています。
【税金の違い】
|
事業を営む形態 |
法人 |
個人事業主 |
|
税金の種類 |
|
|
|
【法人税の詳細】 ①800万円超:23.2% ②800万円以下:15% 【所得税の詳細】 ・課税される所得金額 ①1,000円 から 1,949,000円まで:税率5%、控除額0円 ②1,950,000円 から 3,299,000円まで:税率10%、控除額97,500円 ③3,300,000円 から 6,949,000円まで:税率20%、控除額427,500円 ④6,950,000円 から 8,999,000円まで:税率23%、控除額636,000円 ⑤9,000,000円 から 17,999,000円まで:税率33%、控除額1,536,000円 ⑥18,000,000円 から 39,999,000円まで:税率40%、控除額2,796,000円 ⑦40,000,000円 以上:税率45%、控除額4,796,000 |
||
参考:「No.2260 所得税の税率」|国税庁公式サイト、「法人課税に関する基本的な資料」|財務省公式サイト
法人は、所得金額が800万円を境に税率が異なります。所得金額が800万円を超えると税率が上がりますが、800万円以降はいくら所得が増えても23.2%を超えることはありません。
一方、個人事業主の場合、900万円以上になると税率が33%と法人よりも高くなります。そのため、所得金額が800万円を超えている個人事業主は、法人化することにより節税につながる可能性があります。
税金の違いから見たメリットデメリット
法人と個人事業主では所得に対してかかる税金が異なり、それぞれメリットとデメリットがあります。会社を設立するか個人事業主として起業するか悩んでいる人は、法人と個人事業主の税金の扱いを比較してみましょう。
【税金の違いによるメリットデメリット】
|
事業形態 |
メリット |
デメリット |
|
法人 |
|
|
|
個人事業主 |
|
|
法人の場合、所得金額が800万円を超える事業者は税金の負担を抑えられることや、個人事業主から法人へ転換する「法人成り」の事業者は消費税の納税が2年間免除されるなどのメリットがあります。しかし、「法人住民税」の納税義務が発生することがデメリットであり、赤字事業者であっても支払いが必要となります。
個人事業主の場合、所得金額が800万円以下の事業者は税金の負担を抑えられることや、赤字事業者であれば所得税の支払いが免除されるなどのメリットがあります。しかし、所得金額が800万円を超える事業者は、法人よりも納税額が高額になることがデメリットです。
法人と個人事業主を税金の観点から比較した場合、メリットとデメリットは事業の所得金額により異なります。自身の事業における所得に応じて、どちらの事業形態が適しているかを判断しましょう。
経費の範囲の違い
法人と個人事業主では、経費の範囲も異なります。事業にかかった費用は、法人と個人事業主どちらも経費にできますが、個人事業主は給与や福利厚生などを経費にすることができません。
【法人で経費になるが個人では経費にならない項目】
- 経営者本人の給与と賞与、退職金
- 家族が従業員である場合の給与と賞与
- 福利厚生や健康診断の費用
- 社会保険料
- 出張時の日当
- 住宅費(社宅を利用した場合)
※個人事業主が自宅をオフィスとしている場合は、家賃や電気代を家事按分をして経費計上できる
たとえば、法人の場合は経営者の給与や賞与、退職金を経費として計上できます。個人事業主の場合は売上が「所得」であるため、経営者の給与にはならず経費として計上できません。法人は経費にできる項目が多いことから、個人よりも節税効果が期待できます。
また、法人の場合は、従業員が家族である場合の給与と賞与も経費として計上できます。個人事業主の場合は原則として家族分の給与や賞与を経費として計上することはできませんが、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより経費に含められる可能性があります。
なお、個人事業主の場合、事業にかかわる経費と家事による経費を分けて経費の計算をする「家事按分」を行うことで経費にできる範囲が広がります。自宅兼オフィスで仕事をしている場合は、家賃や水道光熱費、通信費、自動車関連費が対象となります。
ただし、家事按分した経費が事業の必要経費として認められるためには、明確な記録と事業の遂行に欠かせない経費であることが求められます。税務調査で家事按分の修正指示を受けないためにも、プライベートと仕事の支出をはっきり分けておくことが必要です。
経費の範囲の違いから見たメリットデメリット
法人と個人事業主では経費の範囲が異なり、それぞれメリットとデメリットがあります。会社を設立するか個人事業主として起業するか悩んでいる人は、法人と個人事業主の経費の範囲を比較してみましょう。
【経費の範囲の違いから見たメリットデメリット】
|
事業形態 |
メリット |
デメリット |
|
法人 |
|
|
|
個人事業主 |
|
|
法人の場合、個人事業主よりも経費として計上できる項目が多いことがメリットです。しかし、交際費に関しては法人のみに限度額が設けられており、所定の金額を超える部分は経費として申請できず法人税の課税対象となるというデメリットがあります。
個人事業主の場合、交際費に上限が定められていないため、交際費として使用した金額をすべて経費にできることがメリットです。しかし、法人と比較して経費として申請できる項目に制限があるほか、仕事とプライベートの支出を事業者自身で分けて計算しなければならないことがデメリットとなります。
個人事業主が会社設立する際の流れ
個人事業主がもともと行っていた事業を引き継いで会社設立することを、法人成りといいます。個人事業主が法人成りする場合は、通常の会社設立の手続きに加えて、個人事業の廃業手続きや資産と負債の引継ぎ業務などが発生します。
【法人成りの流れ】
|
流れ |
詳細 |
|
①会社設立の手続き |
|
|
②個人事業の廃業手続き |
|
|
③資産および負債の引継ぎ |
|
|
④各種契約物の名義変更および取引先への挨拶 |
|
|
⑤その他 |
|
登記申請を終えたら、個人事業の廃業手続きを行います。廃業から1か月以内に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、所轄の都道府県税事務所へ「事業開始(廃止)等申告書」を提出します。「事業開始(廃止)等申告書」は各都道府県税事務所によって異なるため、公式サイトで確認しましょう。
資産の移行には「売買契約」「現物出資」「賃貸契約」の3つの方法があり、それぞれ手続きやルールが異なります。一般的には「売買契約」で新設した会社に資産を売却するか、または「賃貸契約」で、方法と個人が所有している資産を新設した会社に貸し出します。
負債の移行をする際は、個人事業と新設した会社の両方が負債を引き受ける「重畳的債務引受」と、法人のみで負債を引き受ける「免責的債務引受」があります。銀行からの借受金を新会社へ移行する場合は、債務の引き受け契約を交わすことになるため、どんな方法で債務を移行するかを銀行に相談する必要があります。
その他にも、各種契約の名義変更の手続きや法人口座の開設など、会社設立に必要な手続きには時間も手間もかかります。できるだけ時間をかけず主業務に集中したい人は、登記手続きは司法書士に任せるなど、専門家への依頼を検討してみてください。
まとめ
会社設立と個人事業主による起業では、事業を始める際の手続きや社会的な信用度、税金や経費の範囲など、事業を運営する際のルールが異なります。法人化を検討する際は、それぞれのメリットとデメリットを理解し、収入や売上高をもとに専門家との相談の上慎重に判断しましょう。
個人事業主から法人化する際は、資産や負債の移行手続きも必要です。負債の移行の場合は金融機関との契約も必要であるため、どのような方法で新設する会社に負債を引き継ぐのか、必ず金融機関と相談をしましょう。
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
会社設立のご相談はこちら
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。