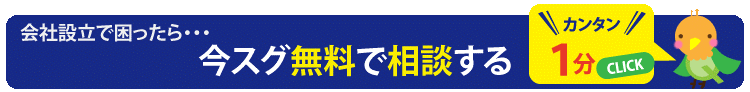法人成りをする際に必要な手続きとは

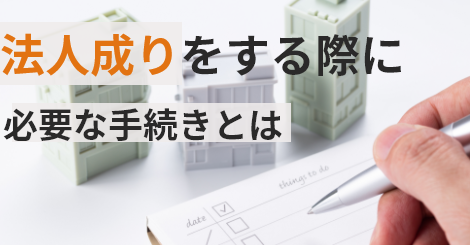
これまで個人事業主として行っていた事業を、法人として新たにスタートさせることは会社を運営する方にとって非常に大きな転換点といえるでしょう。
法人成りすることで、経費として計上できる対象が増え、節税の幅が広がったり、赤字の繰越期間が個人事業主時代の3年間から9年間に増加したりと、様々なメリットが得られますので、個人事業主から法人成りしようと検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法人成り|個人事業が法人に移行する時にしっておきたい7つのメリット
法人成りをするには行わなくてはいけない手続きがたくさんあります。
そこで今回は法人成りをする際に必要な手続きについて詳しく解説します。
1.そもそも法人成りとは
法人成りとは、個人事業主でおこなっていた事業を新会社が引き継いでおこなっていくことです。
ポイントとなるのは、「個人で行っていた事業を引き継ぐことが出来る」ということです。これは全く新しい会社を設立するのとは話が違います。
法人成りをした際に新会社に引き継がれるものは事業内容だけでなく、個人事業主の時の資産や負債まで引き継がれるのです。
ここで言う資産や負債は以下のようなものを言います。
|
資産…具体的には個人事業主時代に所有していた預金の他、売掛金や貸付金などの金銭債権、建物、備品、車両などの固定資産
負債…個人事業主時代に負っていた買掛金や未払金など |
つまり、裏を返せば以前の会社の負債を引き継ぐこと以外、会社を設立する手続きは通常の会社設立と変わらないということです。
2.法人成りの手続き
法人成りの手続きには5つのステップがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
| ステップ1:会社の基本事項の決定
ステップ2:定款を準備し、作成する ステップ3:公証人による定款認証を行う(株式会社の場合) ステップ4:登記書類を作成する ステップ5:法務局に登記申請に行く |
(1)会社の基本事項の決定
まず初めに決めるべきことは会社の形態、 社名、事業目的、本店住所、役員構成、資本金についてです。
①会社の形態を決める
個人事業主から法人成りをした際に、主に使用される会社の形態は株式会社または合同会社です。それぞれに特徴があり、株式会社は知名度と社会的信頼度が高いことが挙げられます。株主など会社の動向をしっかりと監視している人々がいるということに加えて、世間一般に「会社=株式会社」というイメージが付いていて、「株式会社なら何となく信頼できる」という意識が定着しているため、株式会社という文言はブランドイメージとしても有意に働きます。
一方、合同会社は株式会社の半分以下のコストで設立することが可能で、設立時の費用を抑えることが出来ます。また、株式会社には守らなければならない規則等が多いですが、合同会社は定められている制約がそれほど多くはありません。ただし、株式会社と比べ認知度が低く、信頼性の確保が株式会社と比べ困難です。ですが、事業が特定のノウハウに特化していて、一般の多くの人に認知してもらう必要性が高くないのであれば設立コストの安い合同会社が魅力的なはずです。
会社の形態を決める際は自身の状況と照らし合わせて、自分にふさわしいものを選ぶようにしましょう。
②社名を決める
社名は個人事業主時代から引き継いでも新たに名前を付けても良いです。
ただし、社名には会社の形態が分かるように株式会社または合同会社などを付け加えなければなりません。これは会社法の第6条2項に記されている事項であり、決まりです。
また、注意点として同一の住所に同じ社名は使えないのでオフィスが入る建物内にあなたが考えている社名と同じ会社がないかどうかを確認しておきましょう。
③事業目的を決める
事業目的は個人事業主時代の事業内容や新たに開始しようと考えている事業内容OKです。
ポイントとしてはどのような事業を行っている会社なのかを明確にし、その事業を行うことで利益が見込めるかどうかなどを説明できる事業目的にしましょう。
④本住所を決める
本住所は個人事業主時代のオフィスや店舗があれば、そのままその住所で登記してください。ただし、賃貸の自宅を個人事業主のオフィスとして使用していた場合は、そのまま会社として登録してしまうと、物件上の契約違反になる可能性があるので、管理会社と大家さんに確認が必要です。
⑤役員構成を決める
役員構成を決めるといっても、個人事業主から法人化した場合は基本的には1人、もしくは家族を加えた程度でしょう。株式会社、合同会社などに役員は1人から可能なので、それで問題はありません。
⑥資本金を決める
資本金をいくらにしなければいけないという決まりはありません。しかし資本金は会社の財務力を表すものであり、あまりに低く設定すると会社の信用力や融資を受ける際に不利になるかもしれません。ですから低くなりすぎないように設定しましょう。
また、業種によっては許認可を得るのに「いくらの資本金がなければならない」と条件が設定されているため、あなたが行う業種にそのような規定がないかどうかを確認しておきましょう。
会社設立の手続きを始める前に準備するものについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
参考|会社設立の手続きを始める前に用意しておくべき10の項目
(2)定款を準備し、作成する
決定した会社の基本事項の内容を定款に落とし込みます。
定款は会社の基本的な規則や行動指針をまとめたものであり、会社の名称や所在地、株式や機関設計の内容、事業年度を何月から何月までにするかなどを記載します。
定款の作成についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
参考|株式会社の定款作成:19の空欄を埋めるだけの雛形と8つの注意事項
(3)公証人による定款認証を行う(株式会社の場合)
株式会社の場合、定款を作成したら、その内容を地域の公証役場で公証人に認証してもらわなければなりません。というのも公証人に認証されていない定款のことを「原始定款」といい、原始定款では定款としての効力を持たないのです。
ではなぜ株式会社は認証が必要で合同会社などは必要ないのでしょうか?
それは会社の形態が違うからです。
定款認証は所有と経営の分離が行われる株式会社において、所有者と経営者の間で紛争が起こった際に、定款に基づいて「会社がどのような方針を定めているのか」ということを確認することなどで利用します。
一方で合同会社などは所有者と経営者が分かれていません。また、定款は社員全員で決めるため、株式会社ほど紛争が起きにくいという判断から合同会社などは定款認証を行う決まりがないのです。
定款認証は各地域の管轄の公証人役場で行います。
全国の公証人役場はこちらからご確認いただけます。
参考|日本公証人連合会
①定款認証の方法には紙と電子がある
定款認証には紙で印刷した定款を使う場合と、PDFファイルで作成した定款を専用ソフトにより電子署名して、公証役場に送信して認証手続きをする方法の2種類があります。
電子定款の場合は印紙代4万円が必要なくなるので費用を抑えることが出来ます。しかし、どちらのパターンを選んだとしても最終的には公証役場まで定款を取りに行く必要があるので注意しましょう。
定款認証についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
(4)登記書類を作成する
登記申請に必要な書類は以下の通りです。
| 登記申請に必要な書類
法人登記申請書 定款 発起人の決定書 取締役・代表取締役・監査役の就任承諾書 資本金払込を証明する書類 取締役全員の印鑑証明書 印鑑届出書 資本金額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 監査役の就任承諾書 |
それぞれの書類について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
参考|会社設立登記に必要な書類のリストとそれぞれの書類を作成する手順
それぞれの登記様式はこちらからダウンロードすることが出来ます。
(5)法務局で登記申請を行う
登記書類が完成したら、法務局で登記申請を行います。法務局で登記申請を受け付けてもらった日が会社の設立日となります。
各地域の管轄法務局はこちらから確認することが出来ます。
参考|法務局 管轄のご案内
3.法人成りをした後に必要な手続き
法人成りをした後にも行わなければならない必要な手続きが7つあります。
| ステップ1:資産・負債を新会社に引き継ぐ
ステップ2:各種契約の名義変更 ステップ3:税務署に各種届出を提出する ステップ4:新しい会社の業種に合わせて許認可を取る ステップ5:都税事務所への届出 ステップ6:年金事務所への届出 ステップ7:従業員を雇う場合に必要な労働基準監督署・ハローワークへの届出 |
(1)資産・負債を新会社に引き継がせる
法人成りをしたら、個人事業主時代の資産や負債を新しい会社に引き継がせなければなりません。資産・負債の移行には3つの方法があります。
①売買契約
個人事業と会社で「売買契約書」を交わし、個人事業で使用していた財産を売買します。個人事業者である社長と会社で、売買契約書を結び、代金のやりとりをします。
②現物出資
個人事業者であった社長から会社へ、金銭以外の資産を出資する方法です。車や売掛金、そのほかのものも出資可能です。
③賃貸借契約を結ぶ
個人事業主であった社長(あなた)とあなたが設立した会社の間で、「賃貸借契約書」を交わし、賃貸料のやり取りをします。ややこしいですが、これは資産を個人事業主だったあなたの所有としたまま、新しく設立した会社に貸し出すということです。
なお事業用資産・負債を引き継ぐ際には、「財産目録(引き継ぎ資産・負債の一覧表)」、「事業譲渡(営業譲渡)契約書」、「株主総会(取締役会)議事録」などの書類も作成するようにしましょう。
(2)各種契約の名義変更する
個人事業主から法人成りをし、新しく設立した会社を設立したらこれまで個人名義で行っていた契約を会社名義に変更する必要があります。名義変更が必要なものには主に以下のものがあります。
|
(3)税務署に各種届出を提出する
①個人事業を廃業するための届出
法人成りをして新しく会社を設立するということは、これまで行っていた個人事業を辞めるということです。そのため個人事業の廃業に伴う届出を行わなければいけません。提出が必要な書類は以下のものです。
※書類名をクリックすると、ダウンロード先へ移動します。
| 書類名 | 提出期限 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業した日から1か月以内に提出 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出 |
| 給与支払事務所等の廃止届出書 | 廃業した日から1か月以内に提出 |
| 事業廃止届出書 | 事由が生じた場合、速やかに提出 |
提出するには以下の方法があります。
| ①窓口に直接持参する
②郵送で送る ③e-Taxを利用し、オンラインで提出 e-Taxを利用して提出する場合はそれぞれの届出書に該当する項目から提出を行ってください。 |
②会社設立にあたって必要となる届出書類
個人事業を廃業し、新たに会社を設立する際は、以下の提出書類が必要です。
※書類名をクリックすると、ダウンロード先へ移動します。
| 書類名 | 提出期限 |
| 法人設立届出書 | 法人設立の日(設立登記の日)から2か月以内に提出します。 |
| 青色申告の承認申請書 | 法人の設立(設立登記の日)から3か月以内、または最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い方に合わせて提出 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内に提出 |
| 源泉所得税の納期の特例の申請書 | 随時、必要に応じて提出(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出 |
| 所得税の予定納税の7月(11月)減額申請書 | 第1期分及び第2期分の減額申請する場合:7月1日から7月15日までに提出
第2期分のみの減額申請する場合:その年の11月1日から11月15日までに提出 |
提出するには以下の方法があります。
| ①窓口に直接持参する
②郵送で送る ③e-Taxを利用し、オンラインで提出 ④「法人設立ワンストップサービス」で提出 |
e-Taxでは法人設立届出書と減価償却資産の償却方法の届出書を提出することが出来ません。
そのため、オンラインで提出したいと考えている場合は「法人設立ワンストップサービス」での提出をおすすめします。
法人設立ワンストップサービスとはマイナポータルという1つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができます。利用するために必要なものは以下のものです。
|
(4)新しい会社の業種に合わせて許認可を取る
会社を新しく設立した場合、事業内容が個人事業主時代と同じであっても、個人事業としては廃業し、新たに会社を設立しているため新たに許認可が必要となります。
許認可の申請先は以下の通りです。
| ①保健所:飲食業、理・美容業
②都道府県:建設業、宅地建物取引業 ③労働局:有料職業紹介事業、人材派遣業 ④警察署:古物業 |
(5)都道府県税事務所への届出
新しく会社を設立した際には都道府県税事務所に「法人設立届出書」を提出します。他に定款の写し、履歴事項全部証明書も提出が必要です。
会社の本店所在地がある都道府県税事務所が提出先となりますので、各都道府県のホームページから確認してください。
提出方法としては窓口に持っていくか、郵送で送る、あるいはe-Taxでのオンライン申請がありますが、各都道府県ごとに異なりますので、提出前に必ず確認しましょう。
(6)年金事務所への届出
健康保険・厚生年金保険の手続きのため、設立後5日以内に以下の必要書類を年金事務所へ提出する必要があります。
①必要書類
| 必要書類 | 添付書類 |
| 新規適用届出書 | 法人(商業)登記簿謄本、法人番号指定通知書の写し |
| 被保険者資格取得届 | 原則不要。しかし次の場合にはそれぞれ必要となります。
・60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合 就業規則・退職辞令の写し、雇用契約書の写し、「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書 ・国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合 健康保険被保険者適用除外承認申請書 |
| 被扶養者届 | 戸籍謄本または戸籍抄本、年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類、別居をしている場合は仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類 |
| 保険料口座振替納付申出書 | なし |
提出するには以下の方法があります。
| ①窓口に直接持参する
②郵送で送る ③e-Govによる電子申請 ④CD・DVDによる電子媒体による提出 |
ただし、e-Govを利用できるのは新規適用届出書のみで、CD・DVDによる電子媒体を利用する提出も対象となるのは被保険者資格取得届と被扶養者届のみです。
その他の書類は窓口か郵送で提出してください。
日本年金機構の全国の窓口はこちらから確認することが出来ます。
参考|日本年金機構
(7)従業員を雇う場合に必要な労働基準監督署・ハローワークへの届出
労働基準監督署に提出する届出は以下のものです。
|
労働基準監督署に提出する方法は窓口に持参するか、郵送、e-Govによる電子申請があります。
全国労働基準監督署はこちらから確認することが出来ます。
ハローワークに提出する届出は以下のものです。
| 提出書類 | 添付書類 |
| 雇用保険適用事業所設置届(設置の日の翌日から10日以内) | 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、登記簿謄(抄)本等 |
| 雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで) | 金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等) |
提出するには以下の方法があります。
| ①窓口に直接持参する
②郵送で送る ③e-Govによる電子申請 |
ただし、雇用保険適用事業所設置届は郵送で送ることが出来ないので注意をしましょう。
全国ハローワークはこちらから確認することが出来ます。
4.個人事業の確定申告を忘れずに
法人成りをした際、会社の設立などにかかる手続きとは違い忘れられがちですが、個人事業主として最後の確定申告を行う必要があります。
その際、3つの注意しなければいけないポイントがあります。
①個人事業の売上と会社としての売上を区別する
法人の設立日の前後で、個人としての売上とどこからが会社の売上を区別しなければいけません。個人事業主として受けた仕事の入金が法人設立後に行われても、申告する上では個人事業主として申告するのです。
つまり、いつの仕事に対する請求かということが見るべきポイントとなるのです。
②会社設立にかかった経費は分けておく
会社設立にかかった経費はしっかりと分けましょう。設立前にかかった費用であっても、設立のために使われる費用であるのなら、会社としての費用となり、個人事業主としての確定申告には含めません。
③会社のお金と自分のお金をしっかりと区別する
個人事業主時代とは違い、会社となると社長であっても役員報酬として会社のお金をもらうことになります。そのため、個人事業主として稼いだお金である事業所得と役員報酬をもとに計算した給与所得の2種類の所得の申告が必要です。
まとめ
個人事業主から法人成りをするには様々な機関に、様々な届出を行わなければいけません。それぞれの書類ごとに提出方法が異なりますので、事前にきちんと確認をしておく必要があります。
提出書類によっては、期限が決まっている書類もあります。法人成りをしたい時期から逆算してスケジュールには余裕をもって準備をしましょう。「法人成りの手続きをすべて自分で行うのは不安」という方は専門家に依頼するのもひとつの方法です。
弊社株式会社ソラボでは会社設立に関する相談にものっていますので、ぜひ一度お問い合わせください。
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
会社設立のご相談はこちら
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。