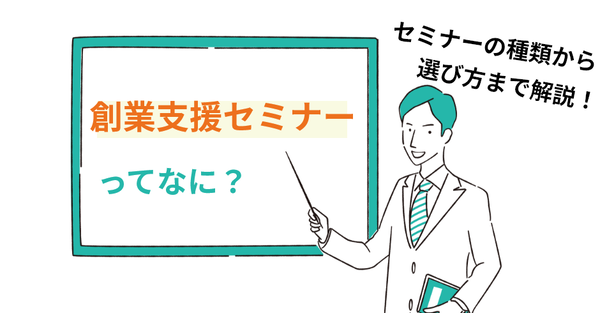高校生が起業する時代?学生起業家になるための手順を解説


学生起業家という言葉を耳にしたことはないでしょうか。
日本では起業するということに対してハードルが高いと感じる人が多いようです。しかし、近頃では学生のうちに起業する若い経営者が増えてきました。中には、高校生ながら起業を志す人も、実際に起業して社会人に交じり仕事をしている人もいます。
そこで、当記事では高校生のうちに起業するにはどうすればよいのか、学生起業家になるための手順を解説していきます。
起業を志したら、まずセミナーや起業プログラムに参加してみる
起業を志したら、セミナーや起業プログラムに参加するなど、行動に移すことが重要です。セミナーや起業プログラムに参加すれば、自分のアイディアがビジネスとして通用するかをプロの目線から判断してもらえるからです。
たとえば、日本政策金融公庫では、高校生ビジネスプラン・グランプリという大会を開いており、参加することで日本公庫の職員にビジネスプランについてアドバイスをもらえます。
高校生ビジネス・グランプリ以外にも、最近では高校生を対象とした起業に関するセミナーやプロジェクトが多数開催されていて、同世代の学生が起業に対してどう考えているかなどを肌で感じることができます。zoomで開催されるセミナーも多く、地域問わず参加することができるので、起業を志している人はセミナーに参加してみて、プロの意見を聞いてみるのをおすすめします。
親権者の同意を得る
高校生が起業するためには、親などの親権者の同意を得る必要があります。
なぜなら、民法第5条で「未成年者が法律行為を行うには親権者の同意を得なければならない」と明記されており、商法第5条では「未成年者が商行為を行うときはその登記をしなければならない」と定められているからです。
会社登記の際、すべての書類に親権者の同意書が必要となるため、起業する旨を親権者と話し合っておきましょう。
資金を必要としない起業アイディアを出す
高校生で起業するなら、資金を必要としないか、またはほとんど必要としない起業アイディアを出しましょう。資金調達の方法が限られている高校生にとっては、資金の必要なビジネスを行うのは実現と継続が難しいためです。
実際に高校生の起業で実績のあるビジネスは、アプリ開発やプログラミング、イベントの企画プロデュースなど、資金を必要としない事業であるケースが多いです。
資金を必要としない起業は、スキルが必要になります。もし自分のスキルに自信がない場合は、先に起業アイディアを出し、伸ばすスキルを決めると良いでしょう。
参考:学生起業の方法とは?アイデアや成功例を紹介 | バーチャルオフィス1
事業内容の需要と競合を調査する
せっかく起業アイデアをだしても、事業開始のタイミングを逃して需要がなくなっていたり、より大きな企業が先に同じ事業を開始していることがあります。起業アイデアを考えることと同時並行で事業内容の需要と競合を調査する必要があります。
起業内容の需要を調べる
起業する事業内容が、現在どれくらいの需要があるか調査しましょう。
おすすめの調査方法は、実際に問題を抱えている人に話を聞くことです。直接話を聞くことができればなお良いでしょう。問題に対して悩んでいる人にアイデアを提案してみて意見を聞くことができます。
事業内容が似ている競合を調べる
起業する事業の世界にどれくらいの競合がいるか調べましょう。
たとえ事業内容が多くの人の悩みを解決する、需要の多いものだとしても、よりメジャーな企業が全く同じ事業を行っていた場合、顧客の獲得が難しくなります。
おすすめの調査方法は、まずwebで検索することが有効です。同じ事業内容を違う言葉で説明していることもあるので、表現の仕方を変えつつ調べてみましょう。
実際に競合先である企業の商品やサービスを使用してみるのも良いでしょう。競合他社にはない付加価値を見つけるきっかけになるかもしれません。
事業名や事業目的などを決める
起業するにあたり、事業名や所在地、事業目的を決めましょう。
どのような事業内容で起業するのか、そのビジネスでどのような問題が解決するのかなど、明確な目的を持っていることで起業後のモチベーションが安定します。
事業目的や事業展開のビジョンなどを詳しく決めると、事業計画が立てやすくなります。事業計画を立てることで、目標のために解決すべき問題を先に抽出し、将来発生するであろう課題の対策をとることができます。
法人の場合、定款を作成する
法人として起業する場合、定款を作成しましょう。
定款とは、会社の設立時に発起人の同意のもと作られる、会社を経営していくための決まりです。株式会社のような法人を起業するとき、定款を作ることが義務付けられています。
定款には、商号(会社の名前)や事業目的、本店所在地などの基本的な情報に加え、発行される株式の数、決済月など経営内容なども記載しなければなりません。
定款の作成は慣れない人が行うと時間がかかるため、専門家に依頼して作成してもらうことも選択の一つです。
また、15歳以上の未成年者が定款を作成するとき、定款として認証するために、次の4つの書類が必要になります。
| | 未成年者本人の印鑑登録証明書 |
|---|---|
| | 親権者の印鑑登録証明書 |
| | 戸籍謄本 |
| | 親権者の実印を押した同意書 |
以上4つの書類を、作成した定款とともに公証役場に提出する必要があります。
法人として起業しようと考えている人は、15歳以上で印鑑登録が可能なため、自身の印鑑を作成し、印鑑登録証明書を確保しておきましょう。
公的機関に開業申請の書類を提出する
公的機関に開業の申請のために書類を提出しましょう。
起業の形が個人事業主か法人かで開業の申請にかかる費用が違います。
株式会社、個人事業主という2つの主なビジネスの方法と、開業の申請にかかる最低金額を以下の表にまとめました。
| 株式会社 | 個人事業主 | |
|---|---|---|
| 定款の収入印紙代 | 4万円 | 不要 |
| 定款の認証手数料 | 3万円 | 不要 |
| 定款の謄本手数料 | 2千円 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円 | 3万円 |
| 資本金 | 1円~ | 1円~ |
| 費用合計 | 約23万円~ | 約3万円 |
新社会法によって、資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました。しかし、許認可が必要な事業の場合、許認可を受ける要件のなかに資本金の額が設けられていることがあるため、自身の事業内容の許認可の要件なども調べておきましょう。
個人事業主の場合は税務署に開業届を提出
15歳以上の未成年の場合、法務局で未成年者登記を行った後、税務署に開業届を提出します。
高校生は開業届を提出する前に未成年者登記をし、「未成年者登記簿」を取得しなければなりません。未成年者登記とは、未成年者が自分の名前で商売をするということを法務局に申請することです。
未成年者登記は、未成年者本人の申請で行われますがその際、以下の書類のどちらかがを用意しましょう。
- 親権者などの法定代理人の許可を得たことを証明する書面
- 未成年者登記の申請書に法定代理人の記名と押印があるもの
未成年者登記簿を取得後、事業を行う地域の所轄の税務署に開業届を提出しましょう。
法人の場合は法務局に登記申請書類等を提出する
15歳以上の未成年の場合、定款を作成した際に用意した4つの書類を合わせて、以下の14の書類を用意し、法務局に提出しましょう。
| | 未成年者本人の印鑑登録証明書 |
|---|---|
| | 親権者の印鑑登録証明書 |
| | 戸籍謄本 |
| | 親権者の実印を押した同意書 |
| | 登記申請書 |
| | 登録免許税納付用台紙 |
| | 定款 |
| | 発起人の決定書 |
| | 設立時取締役の就任承諾書 |
| | 設立時代表取締役の就任承諾書 |
| | 設立時取締役の印鑑証明書 |
| | 資本の払い込みがあったことを証明する書面 |
| | 印鑑届出書 |
| | 登記すべき事項を記載した書面またはCD-R |
提出する書類をすべて用意したら、提出先である法務局が会社の住所を管轄にしているところであるか確認しましょう。提出先が間違ってしまうと、書類がすべて揃っていても申請が受理されないため気をつけましょう。管轄法務局については、法務局ホームページの管轄のご案内より確認することができます。
まとめ
PCやスマートフォンが身近にある現在、高校生が起業することは昔ほど難しいことではなくなりました。起業の方法について押さえておき、身近な問題に目を向けて起業アイデアを生み出してみましょう。
当記事では高校生が起業するときの手順を解説しましたが、未成年であるため、親権者の同意と協力が不可欠です。
新しいビジネスアイデアを考え挑戦することは起業家として大事なことですが、周囲の大人を味方につけサポートしてもらうことも重要なスキルの一つです。
学生起業家を応援している起業家もいるため、起業に興味がある人はSNSなどで情報を発信している人の話を聞いてみてはいかがでしょうか。
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
会社設立のご相談はこちら
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。