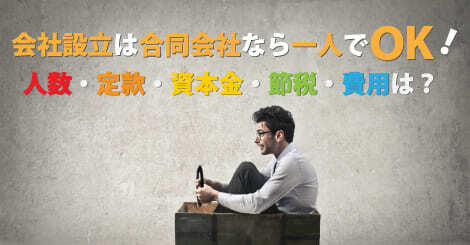会社設立の手続きの流れをフェーズ別の注意点から解説

会社設立というと複雑な手続きや費用のことが頭をよぎり、何から手をつければ良いのか悩んでしまうかもしれません。しかし、法人化は事業の信用を高め、税制面で有利になるなど、ビジネスを次のステージに進めるための重要なステップです。
会社設立をする時には、まずは全体像を把握しておくことをおすすめします。また、実際の会社設立の手続きは最低でも6つのステップを踏んでいく必要があるため、事前に各フェーズで何をするか、その注意点を含めて確認しておくと良いでしょう。
この記事では、会社設立の手続きの流れをフェーズ別の注意点から解説していきます。煩雑な手続きを代行してもらうのに専門家に依頼するべきなのかもあわせて解説しているので、会社設立を検討している人は確認してみてください。
check
会社設立の手続きは、専門家への依頼で手間と時間を大幅に削減できます。
当サイトを運営するソラボグループは、会社設立から設立後の資金繰り・税務までワンストップでサポートいたします。
- 煩雑な手続きに時間をかけたくない
- 専門家のサポートでスムーズに会社を設立したい
- 設立後の資金調達や税務もまとめて相談したい
上記のような方は、ぜひ一度ソラボグループに会社設立の無料相談をしてください。
全国対応・24時間受付 会社設立の無料相談をする会社設立を始める前に知るべき全体像
会社設立を検討している際には、事前に以下の様な項目について把握しておくことが必要です。
【事前に把握しておくべきこと】
- 法人形態の選択肢
- 会社設立にかかる費用
- 会社設立に必要な準備物
これらの全体像を把握せず進めると、会社設立の手続き中にトラブルや予期せぬ出費につながる可能性があります。とくに、設立後の事業展開や資金調達を見据えた法人形態の選択、発生する費用の正確な把握は、経営判断の基盤となります。
法人形態に悩む人や自社の場合いくらで会社が設立できるのか知りたい人は、当サイトを運営するソラボグループにお問い合わせください。事前準備の段階から専門家を交えることで、本業に集中しつつ、設立後の経営を見据えた最適な判断が可能になります。
法人形態の選択肢
会社設立をする時に知っておくべき事前知識として、法人形態があります。
日本において一般的に設立される法人形態には、主に株式会社と合同会社が存在します。これらの法人形態は設立費用や意思決定の仕組み、出資者の責任範囲、資金調達の容易さなどの点で違いがあり、どちらの形態を選ぶかは事業の目的、将来的な規模、経営戦略によって異なります。
【株式会社と合同会社の比較】
|
項目 |
株式会社 |
合同会社 |
|
特徴 |
所有と経営が分離、社会的信用が高い |
所有と経営が一体、経営の自由度が高い |
|
設立費用 |
定款認証費用や登録免許税が高め |
定款認証が不要なため、登録免許税のみで済む |
|
意思決定 |
株主総会や取締役会での決議が必要 |
社員(出資者)全員の同意で決議、機動的 |
|
出資者の責任 |
原則として出資額を限度とする(有限責任) |
原則として出資額を限度とする(有限責任) |
|
資金調達 |
株式の発行により多様な方法で資金調達が可能 |
外部からの資金調達は比較的困難 |
|
社会的信用 |
一般的に高く、取引先や金融機関から信頼を得やすい |
株式会社に比べるとまだ浸透度が低い場合がある |
たとえば、多くの人から出資を募り大規模な事業展開を目指す場合や上場を目指すのであれば、社会的信用度が高い株式会社が適しています。一方、少人数でスピーディに事業を開始したい、設立費用を抑えたい、経営の自由度を重視したい場合は、合同会社が有利です。特に合同会社は、出資者と経営者が同一であることが多く、すばやい意思決定が可能です。
自身のビジネスモデルに合致した法人形態を選ぶことは、会社設立後の事業運営を円滑に進める上で不可欠です。それぞれの特徴をよく理解し、自社にとって最適な選択をすることが、成功への第一歩となるでしょう。
check
会社設立の手続きは、専門家への依頼で手間と時間を大幅に削減できます。
当サイトを運営するソラボグループは、会社設立から設立後の資金繰り・税務までワンストップでサポートいたします。
- 煩雑な手続きに時間をかけたくない
- 専門家のサポートでスムーズに会社を設立したい
- 設立後の資金調達や税務もまとめて相談したい
上記のような方は、ぜひ一度ソラボグループに会社設立の無料相談をしてください。
全国対応・24時間受付 会社設立の無料相談をする会社設立にかかる費用
会社設立をする時に知っておくべき事前知識として、会社設立に掛かる費用があります。
会社設立には、主に国や公証役場へ支払う「法定費用」と、それに付随する「実費」が発生します。とくに株式会社と合同会社では法定費用の内訳や金額が異なるため、自身の選択する法人形態に応じた費用を把握しておくことが重要です。
【会社設立に掛かる費用】
|
費用項目 |
株式会社(目安) |
合同会社(目安) |
|
定款印紙代 |
4万円(電子定款の場合は0円) |
4万円(電子定款の場合は0円) |
|
定款認証手数料 |
約5万円(資本金や目的数による変動あり) |
0円(定款認証が不要) |
|
定款謄本交付手数料 |
約2,000円(1枚250円×ページ数) |
0円(定款認証が不要) |
|
登録免許税 |
資本金の0.7%または15万円のいずれか高い方(例:資本金2,000万円の場合14万円) |
資本金の0.7%または6万円のいずれか高い方(例:資本金1,000万円の場合7万円) |
|
会社代表印作成費用 |
1万円~3万円程度(素材やデザインによる) |
1万円~3万円程度(素材やデザインによる) |
|
印鑑証明書取得費用 |
1通300円程度(複数枚必要) |
1通300円程度(複数枚必要) |
|
謄本取得費用 |
1通600円程度 |
1通600円程度 |
|
専門家報酬 |
0円~10万円程度(依頼範囲や専門家による。自分で手続きする場合は不要) |
0円~5万円程度(依頼範囲や専門家による。自分で手続きする場合は不要) |
会社設立でかかる費用は専門家への報酬は依頼範囲や選ぶ専門家によって変動し、自身で手続きを行う場合は不要です。しかし、専門家に依頼することで、時間や手間を大幅に削減できるだけでなく、法務や税務上のミスを防ぐことにもつながります。
なお、高額な登録免許税は特定創業支援等事業を利用することで半額にできる可能性がある他、専門家を通して電子定款を行うことで印紙代を0円にできます。会社設立の費用を抑えたい、または特定創業支援等事業の適用可否や具体的な費用感について知りたい場合は、ソラボグループにご相談ください。
全国対応・24時間受付 会社設立の相談をする会社設立に必要な準備物
会社設立をする時に知っておくべき事前知識として、必要な準備物があります。
会社設立の手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類や物品を漏れなく準備しておくことが重要です。準備不足は手続きの遅延や二度手間につながるため、以下のリストを参考に事前に確認して揃えておきましょう。
【必要な準備物】
|
準備物項目 |
概要と注意点 |
|
会社代表印(実印) |
|
|
銀行届出印・角印 |
|
|
個人の印鑑証明書 |
|
|
個人の実印 |
|
|
身分証明書 |
|
|
資本金 |
|
|
発起人決定書 |
|
|
印鑑届出書 |
|
|
発起人会議事録 |
|
設立する事業内容によっては、上記の他に準備が必要なものもあります。たとえば、飲食店で法人を設立する場合、食品衛生法に基づく営業許可申請書や、店舗の見取り図、食品衛生責任者の資格を証明する書類などが追加で必要になる場合があります。
上記の準備物を揃えることで、会社設立の手続きを円滑に進めることが可能になります。法的な要件を満たす書類の準備や、各種印鑑の作成は、専門的な知識が必要となる場合もあるので、不明な点があれば、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
会社設立の手続きの流れ
会社設立の手続きの流れは次のような手順で行っていきます。
【手続きの流れ】
- 会社基本事項の決定
- 定款の作成と認証
- 資本金の払い込み
- 設立登記の申請
- 税務署への届出
- 年金事務所への届出
- ハローワークへの届出
会社設立の手続きは、多岐にわたる項目を段階的に進める必要があります。これらの手順を正確に理解し、計画的に実行することで、スムーズかつ確実に会社を設立できます。不明な点があれば専門家に相談し、正確な手続きを心がけましょう。
会社基本事項の決定
会社設立の手続きの流れの最初のステップ、会社基本事項の決定です。
会社基本事項の決定では、会社の骨格となる「商号(会社名)」「事業目的」「本店所在地」「資本金の額」「役員の構成」などを具体的に定めていきます。これらの事項は会社の定款に記載され、将来の事業活動の方向性や対外的な信用にも影響を与えるため、慎重に検討することが重要です。
【会社基本事項の例】
|
会社基本事項 |
概要と決定時の注意点 |
|
商号(会社名) |
|
|
事業目的 |
|
|
本店所在地 |
|
|
資本金の額 |
|
|
役員の構成 |
|
これらの基本事項を決定するうえでは、設立後の事業運営や税務、将来の資金調達まで見据えて検討することが特に重要です。たとえば、事業目的の記載漏れは追加登記の手間を発生させるだけでなく、特定の許認可取得の妨げとなる可能性もあります。また、資本金の額は会社の信用力に直結するため、単なる初期費用としてではなく対外的な印象や創業融資の審査基準、消費税の免税期間など複数の側面から最適な金額を検討すべきです。
これらの基本事項を事前に具体的に決定し、関係者間で認識を共有しておくことで、その後の定款作成や登記手続きを円滑に進めることができます。あいまいな点があると、後々の手続きで修正が必要となり、時間や手間が増える原因となるため注意しましょう。
定款の作成と認証
会社設立の手続きの流れの2つ目のステップは、定款の作成と認証です。
定款は会社の組織や活動の根本原則を定めた重要な書類であり、会社基本事項で決定した内容を記載します。定款に記載する事項は会社設立後の運営に大きな影響を与えるため、正確かつ法的に問題がないように作成することが不可欠です。
定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、記載漏れや不備があると登記ができなかったり、後々のトラブルの原因となったりする可能性があります。株式会社を設立する場合は、作成した定款の認証手続きが必須です。
【諦観の記載事項】
|
記載事項の種類 |
概要 |
|
絶対的記載事項 |
|
|
相対的記載事項 |
|
|
任意的記載事項 |
|
一方、合同会社を設立する場合は定款の認証は不要です。しかし、定款自体の作成は必要であり、記載内容に不備がないように慎重に作成する必要があります。電子定款を利用すれば、収入印紙代の4万円が不要となるため、合同会社設立時の費用を抑えたい場合は検討してみると良いでしょう。
定款の書き方には決まったフォーマットはありませんが、認証を受けるのには体裁が整っている必要があり、知識がない状態で作成するのは難しいです。自作が難しいと判断した場合は、専門家と作成することを検討してみてください。
全国対応・24時間受付 会社設立の相談をする資本金の払い込み
会社設立の手続きの流れの3つ目のステップは、資本金の払い込みです。
資本金の払い込みは、発起人がそれぞれ定めた出資額を発起人代表の個人銀行口座に入金する必要があります。この際、現物出資を行う場合を除き、現金で払い込むことが一般的です。払い込みが完了したら、その事実を証明する「払込証明書」を作成します。
払込証明書は、通帳のコピー(表紙、裏表紙、入金が確認できるページ)を添付し、代表取締役となる発起人が証明する形式で作成します。払い込みの期日に厳密な定めはありませんが、定款作成後の日付で、設立登記申請日よりも前の日付にする必要があります。
資本金の払い込みが完了して払込証明書が用意できたら、設立登記の準備が整います。この証明書は、登記申請の際に添付書類として提出するため、正確に作成し、大切に保管しておきましょう。
設立登記の申請
会社設立の手続きの流れの4つ目のステップは、設立登記の申請です。
設立登記の申請は、定款認証と資本金の払い込みの完了後に必要書類を揃えて本店所在地を管轄する法務局へ申請することで行います。申請後、通常1週間から2週間程度で登記が完了し、会社の登記事項証明書が取得できるようになります。
【登記申請に必要な書類】
|
書類名称 |
概要と注意点 |
|
設立登記申請書 |
|
|
定款 |
|
|
払込証明書 |
|
|
印鑑証明書 |
|
|
印鑑届出書 |
|
これらの書類に記載漏れや誤りがあると登記が却下され、手続きが遅れる原因となります。とくに登記申請書は専門的な知識を要する会社の情報を正確に記載する必要があるため、慎重に作成する必要があります。
登記が完了すると、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになり、これで会社としての法人格が正式に認められます。この登記簿謄本は税務署や年金事務所への届出、銀行口座開設など、様々な手続きで必要となるため、大切に保管して必要な部数を取得しておきましょう。
税務署への届出
会社設立の手続きの流れの5つ目のステップは、税務署への届出です。
税務署への各種届出を行うことで法人税や消費税などの納税義務が確定し、税務上の様々な優遇措置を受けることが可能になります。届出を怠ると税務上の不利益を被る可能性があるため、設立登記後速やかに手続きを進める必要があります。
【税務署に提出する書類】
|
届出書の名称 |
概要と注意点 |
|
法人設立届出書 |
|
|
青色申告の承認申請書 |
|
|
給与支払事務所等の開設届出書 |
|
それぞれの書類には提出期限が定められています。とくに青色申告の承認申請書は期限内に提出することで将来的な節税メリットを享受できるため、忘れずに提出することが重要です。また、消費税の納税義務の免除を受けたい場合は、消費税に関する届出も検討する必要があります。
これらの税務署への届出は、会社の設立後に税務上のルールに則って事業を運営していくための基盤を築くことになります。不明な点や、どの届出が必要か判断に迷う場合は、税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
年金事務所への届出
会社設立の手続きの流れの6つ目のステップは、年金事務所への届出です。
会社を設立して法人として事業を開始すると、社会保険への加入が義務付けられます。社会保険への加入は病気や老後の生活保障に関わる重要な制度であり、代表者一人の会社であっても会社の義務を果たすためにも必ず手続きを進める必要があるためです。
会社設立後に事業所として保険関係が成立した日から5日以内に、管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険・新規適用届」を提出する必要があります。保険料は役員報酬や従業員の給与によって決まるため、事前に概算を把握し、会社の資金計画に含めておくことが重要です。
ハローワークと労働基準監督署への届出
会社設立後に雇用を行う場合は、ハローワークと労働基準監督署への届出が必要になります。会社が従業員を雇用する際には、労働保険と労災保険加入の手続きも必要になるためです。
【雇用を行う際に届出が必要になる書類】
|
書類名 |
提出先 |
提出期限 |
|
雇用保険適用事業所設置届 |
ハローワーク |
雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
|
雇用保険被保険者資格取得届 |
ハローワーク |
従業員を雇用した日の翌月10日まで |
|
労働保険関係成立届 |
労働基準監督署 |
事業開始日から10日以内 |
これらの届出にはそれぞれ提出期限が定められています。届出を怠ると従業員が適切な保険給付を受けられなくなるだけでなく、会社側が罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。また、労災保険については労働基準監督署への届出も必要となる点も把握しておくべきでしょう。
会社設立は専門家に依頼するべきか
会社設立は、自分で行うか専門家に依頼するかの2つのパターンがあります。それぞれの手法にはメリットとデメリットがあり、主に費用と時間のどちらを取るかの選択になります。
【手段別のメリットとデメリット】
|
会社設立の手段 |
メリット |
デメリット |
|
自分で行う |
|
|
|
専門家に依頼する |
|
|
自分で設立する場合、専門家への謝金としてかかる10万円程度の費用を浮かせることができます。ただし、全ての準備から申請までを自分で行うには、20時間から30時間程度の時間が必要になると言われており、慣れない手続きによる失敗のリスクも伴います。
これらのポイントから、費用を優先するか、時間と確実性を優先するかを考慮し、自分にとって最適な方法を決定すると良いでしょう。なお、ソラボグループに依頼される場合の手数料は66,000円ですが、電子定款認証で印紙代の40,000円が差し引かれるので、実質26,000円の費用上乗せで会社設立が可能です。会社設立を専門家に依頼したい場合は、ぜひソラボグループにご相談ください。
全国対応・24時間受付 会社設立の相談をするこの記事を書いたライター

ソラボ編集部
会社設立のご相談はこちら
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。