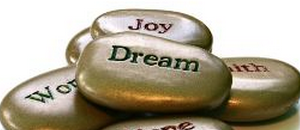資金調達ラウンドとは?6つの段階を解説


スタートアップの成長には、適切な資金調達の戦略が必要です。「資金調達ラウンド」と呼ばれる資金調達のフェーズは、スタートアップの成長段階を投資家に示す指標となります。そのため、投資家側の目線では「投資ラウンド」と呼ばれることもあります。
当記事では、資金調達のフェーズによって異なる目的や特徴を6つのラウンドごとに解説していきます。また、事業ステージに応じた資金調達方法も解説するので、資金調達に向けてラウンドの概要を理解しておきたい人は参考にしてみてください。
資金調達ラウンドとはスタートアップが自社の成長フェーズを示す指標
資金調達ラウンドとは、スタートアップが事業の成長や拡大に必要な資金を調達する際に「自社が今どの成長フェーズにいるのか」を投資家に向けて示す指標です。
スタートアップ企業がどの成長段階にあるのかによって、資金調達の内容や投資家の系統も異なるため、ラウンドは資金調達を円滑に進めるために有効な目安となります。
<スタートアップの成長フェーズに応じた資金調達ラウンド>
| ラウンド | 成長フェーズ | 資金調達の目的 |
|
エンジェル |
アイデア段階 |
・アイデアの具体化 |
|
シード |
試作・市場テスト |
・プロトタイプの開発 |
|
プレシリーズA |
市場投入準備 |
・製品の改良 |
|
シリーズA |
初期拡大 |
・事業基盤の強化 |
|
シリーズB |
成長・拡大 |
・顧客基盤の拡大 |
|
シリーズC以降 |
収益性確保・上場準備 |
・新市場進出 |
たとえば、プロトタイプ開発と市場調査を終えた企業は、プレシリーズAからシリーズAへの移行を見据えて具体的な事業計画を作成し、投資家との交渉を進めます。投資家は、企業がこの段階の課題を解決しているかや、シリーズA規模の投資で期待されるリターンが見込めるかを慎重に判断します。
投資家から見て企業の成長がシリーズAの水準に達していないと判断した場合には、希望する額の資金調達が叶わない可能性もあります。そのため、企業側は資金調達に臨む際、成長計画と今後の展望を十分にアピールし、ラウンドの進行に妥当性があることを投資家に示す必要があります。
資金調達ラウンドは、投資家がスタートアップへの投資を検討する際に、投資先企業の成長フェーズを把握する目安となります。資金調達を行う企業は、自社のフェーズを投資家に示せるよう、各ラウンドの投資目的や調達額の目安などを確認しておきましょう。
①エンジェル
エンジェルラウンドは、スタートアップが事業を始める前後に行われる最初の重要なステップであり、アイデアを具現化するための準備段階です。このフェーズでは、製品アイデアを具体化し、初期市場調査や試作品の開発が行われます。
エンジェルラウンドは、スタートアップの基盤を構築するための時期であり、資金だけでなく、事業を進めるための知見や人脈も得られる場となります。
<エンジェルラウンドの概要>
| 項目 | 内容 |
|
成長目的 |
アイデアの具体化、試作品開発、人材確保 |
|
資金調達額の目安 |
数百万円~数千万円 |
|
主な投資家 |
エンジェル投資家、個人投資家 |
|
主な活用例 |
・製品コンセプトの確立 |
エンジェル投資家は、スタートアップや創業初期の企業に資金を提供する個人投資家であり、起業やIPOの経験を活かして成長に向けたアドバイスを提供することもあります。こうした支援を得られれば、資金面だけでなく事業の初期サポートも期待できます。
一方、一般の個人投資家はリターンを重視して幅広い資産に投資します。そのため、エンジェル投資家とは異なり、事業への深い関与は期待できない場合もありますが、少額での資金提供を受けるための選択肢となります。
エンジェルラウンドでは、自己資金を含めた少額ずつの資金調達が行われる傾向にあります。また、投資家からの支援を受ける場合、今後は株主として経営に関与する可能性もあるため、投資家は慎重に選び良好な関係性を築いておきましょう。
②シード
シードラウンドは、スタートアップが事業アイデアを具体化し、ビジネスモデルを構築するための段階です。このフェーズでは、試作品の開発や初期市場調査を行い、製品やサービスの受容性を検証します。
また、法人設立やチームの体制づくりといった基盤構築も進められるため、スタートアップにとって次の成長ステージへ進むための準備期間といえます。
<シードラウンドの概要>
| 項目 | 内容 |
|
主な活用例 |
・法人設立の費用 |
|
成長目的 |
ビジネスモデルの確立、市場テスト |
|
資金調達額の目安 |
数千万円 |
|
主な投資家 |
エンジェル投資家、シードベンチャーキャピタル(VC) |
シードラウンドは、製品やサービスの構想を具体化し、本格的な検証作業を進める段階です。このフェーズでは、試作品を開発して初期ユーザーのフィードバックを収集し、製品の改良点や市場での競争力を明らかにします。また、ターゲット市場を分析し、顧客ニーズを深掘りすることで、事業の方向性を具体化していきます。
この段階での支出は、法人設立費用、初期メンバーの人件費、オフィス賃料など、事業運営の基盤を整えることが中心です。そのため、事業アイデアだけでなく、実現可能な計画を提示し、投資家に事業の成長性を納得させる必要があります。
資金提供者としては、シード特化型ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家が重要な役割を果たします。資金調達だけでなく、これらの投資家との長期的なパートナーシップを構築することで、次の成長段階に進むための基盤をさらに強化できます。
③プレシリーズA
プレシリーズAは、製品が市場に投入され、利用者からのフィードバックを活かして改良を重ねる段階です。このフェーズでは、製品の品質向上や市場での立ち位置を固めるための資金が求められます。
<プレシリーズAの概要>
| 項目 | 内容 |
|
成長目的 |
製品の改善、市場基盤の強化 |
|
資金調達額の目安 |
数千万円~数億円 |
|
主な投資家 |
ベンチャーキャピタル(VC)、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC) |
|
主な活用例 |
・初期顧客への導入キャンペーン実施 |
プレシリーズAは、プロトタイプを利用者に提供し、製品やサービスが市場で通用するかどうかを検証する段階です。売上はまだ十分に上がらず支出が続くため、スタートアップにとって正念場といえます。
この段階の資金調達は、プロダクトマーケットフィット(以下、PMF)に近づいているものの、まだ達成していない状況で行われます。PMFとは、自社の製品やサービスが顧客に受け入れられた状態を指し、PMFを達成できない企業はその後の資金調達が難航する可能性が高くなります。
資金調達額は目安として数千万円から数億円が必要となってきます。一般のベンチャーキャピタル(VC)に加え、企業との連携を重視するコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)も新たな選択肢として加わります。プレシリーズAの資金調達を活用して製品をさらに改良し、市場での基盤を固めましょう。
④シリーズA
シリーズAは、製品が市場で受け入れられたことを示すPMFの達成を前提に、事業の成長基盤を整える重要な資金調達の段階です。この段階では、ユーザー拡大や売上向上を目指し、認知度を高めて新しい顧客を増やすためにマーケティングやブランド力の強化が行われます。
<シリーズAの概要>
| 項目 | 内容 |
|
成長目的 |
PMFの実現、マーケティング強化 |
|
資金調達額の目安 |
数億円 |
|
主な投資家 |
ベンチャーキャピタル(VC)、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC) |
|
主な活用例 |
・デジタルマーケティングキャンペーン |
シリーズAの段階では、事業が成長に伴い顧客が増え始め、商品やサービスの提供が本格化しますが、収益が安定する前で資金が不足しがちな時期でもあります。そのため、成長を支えるために、優秀な人材の採用や認知度向上に向けたマーケティング強化が不可欠です。
たとえば、インターネット広告やプロモーションによってブランドの認知度を高めることや、ユーザーの利用データを収集してサービス改善に活用します。また、成長に伴って必要となる人材増員や組織体制の整備にも資金が活用されます。
シリーズAでは、成長中の企業に投資を行うベンチャーキャピタル(VC)や、大企業が運営する投資部門であるコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から数億円規模の資金を調達することになります。このフェーズでの調達期間は半年以上と想定しておきましょう。
⑤シリーズB
シリーズBは、事業が安定した収益基盤を持ち、さらなる拡大を目指すための資金調達です。この段階では、すでに製品やサービスが市場で一定の評価を得ており、次のステップとして顧客基盤の拡大や新市場の開拓が求められます。
<シリーズBの概要>
| 項目 | 内容 |
|
成長目的 |
顧客基盤拡大、マーケティング強化 |
|
資金調達額の目安 |
数億円~数十億円 |
|
主な投資家 |
ベンチャーキャピタル(VC)、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)、PEファンド |
|
主な活用例 |
・広告やイベントによるブランディング活動 |
シリーズBでは、製品やサービスが市場で確かな評価を得ており、さらなる成長を支えるための拡張が中心となります。
たとえば、新たな地域への進出や、多店舗展開を通じた市場シェアの拡大が課題となります。また、既存顧客の満足度向上に向けた顧客サポートの強化も、このフェーズでの取り組みとして挙げられます。
この段階では、事業運営における効率性が一層求められ、組織体制の見直しや強化も重要視されます。特に、ユニットエコノミクス(UE)の達成が収益構造の確立に直結します。UEとは、1顧客あたりの収益性を示す指標で、顧客基盤の拡大が利益増加につながるかどうかを評価する基準となります。UEを達成することで、投資家の信頼を得るとともに、次の成長ステージへの準備が整います。
⑥シリーズC以降
シリーズC以降のラウンドは、事業が黒字化し、安定した収益基盤を確立したうえで、更なる成長や出口戦略に向けた取り組みを進める段階です。このフェーズでは、IPO(新規株式公開)やM&A(事業売却)を視野に入れ、新規市場や海外市場への進出、事業の多角化が主な目標となります。
<シリーズC以降の概要>
| 項目 | 内容 |
|
成長目的 |
事業の成熟、新市場・海外展開 |
|
資金調達額の目安 |
数十億円以上 |
|
主な投資家 |
PEファンド、戦略パートナー |
|
主な活用例 |
・新市場におけるオフィスの設置 |
シリーズC以降では、事業が安定した収益基盤を持ち、上場や事業売却といった出口戦略の準備が進められます。多くの企業がシリーズCまたはDで上場や事業売却のタイミングを見極め、今後の事業の方向性を決める時期となります。
資金調達の手段には、PEファンド(未上場企業に投資して経営支援を行い、企業価値を高めてIPOや売却によって利益を得るファンド)や、戦略パートナーからの投資が加わります。これにより、企業同士が協力してシナジー効果を生み出し、単独では提供できない新しいサービス展開も期待されます。
特にシリーズDまで進む企業は、新製品の開発や海外展開に資金を積極的に投入し、更なる成長を図る傾向にあります。一方で、シリーズCで収益が安定した段階でEXITを選択する企業も多く、資金の活用方法や上場準備の進捗状況は企業の状況ごとに異なります。
なお、上場や売却の交渉にはおおむね半年程度は必要であると留意しておきましょう。企業はシリーズC以降、それぞれの成長ステージや市場環境に応じて、上場や事業売却といった出口戦略を決定し、最終的なステージに向けた最適な選択を図ります。
事業ステージに応じて資金調達の内容も変わっていく
資金調達ラウンドは、スタートアップ企業の「事業ステージ」に沿って進んでいきます。ラウンドは「資金調達の段階」を示している一方、事業ステージは「企業の成長段階」を示しているというイメージです。
スタートアップが創業し、事業を軌道にのせるまでの過程は「シード」「アーリー」「ミドル」「レイタ―」の4段階に区分されています。どの事業ステージで、どのラウンドの資金調達が行われていくのかを確認しておきましょう。
<事業ステージ別ラウンドと資金調達の特徴>
| 事業ステージ | ラウンド | 資金調達の特徴 |
|
シード |
・エンジェル |
・自己資金やエンジェル投資家からの資金調達 |
|
アーリー |
・プレシリーズA |
・VC、CVCからの資金調達 |
|
ミドル |
・シリーズB |
・PEファンド、プロパー融資など調達先が広がる |
|
レイタ― |
・シリーズC以降 |
・戦略パートナーも加わり大規模な調達が可能 |
シード期は、製品やサービスをリリースする前後の段階で、多方面からの小規模な資金調達を目指します。この時期には、エンジェル投資家や個人投資家が主な資金提供者となります。
事業が成長してアーリー期やミドル期に入ると、製品が市場に受け入れられていることを示す「PMF」や、顧客ごとの収益性を示す「UE」の達成が重要になります。この段階では、より多額の資金が必要となり、ベンチャーキャピタル(VC)やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の関与が増加します。
さらにレイター期では、上場や売却を目指すための準備として、PEファンドや戦略パートナーからの大規模な資金調達が行われます。
企業は事業ステージに応じた資金調達を行うことで、次の成長段階への準備を整え、投資家と協力して事業を発展させる環境を築けます。つぎは各ステージにおける資金調達の方法やポイントを確認してみましょう。
シード期の資金調達
シード期の資金調達は、事業のアイデアを形にして具体化する段階で行われます。シード期は「エンジェル」「シード」のラウンドに該当し、商品・サービスの構想を練ることや試作品の製作、市場調査を実施するための資金が必要です。
事業がまだ軌道に乗っておらず収益が安定しない段階であるため、少額の資金を多方面から調達することが特徴です。エンジェル投資家やシード特化型のベンチャーキャピタル(VC)からの出資のほか、日本政策金融公庫の創業融資制度なども有効な資金源として活用されています。
<シード期の資金調達概要>
| 項目 | 内容 |
|
ラウンドのフェーズ |
エンジェル、シード |
|
資金調達方法 |
・自己資金 |
|
リスク・注意点 |
エンジェル投資家からの出資は経営の自由度が下がる可能性もある |
シード期の資金調達のポイントは、「小額を幅広く集める」ことです。この段階では、製品やサービスに実績がないため、出資を断られることも多く、大きな金額の調達は難しい時期です。
そのため、自己資金や親しい関係者からの借り入れに加え、エンジェル投資家やVC、補助金などを組み合わせ、少しずつ資金を調達することが推奨されます。
また、エンジェル投資家やVCからの出資、および補助金には返済義務がないため、収益が不安定なシード期でも経営への負担が軽減される利点があります。
ただし、エンジェル投資家やVCからの出資を受ける場合、出資者が株主として経営に関与する可能性があります。出資者の選定や契約時の条件確認には慎重を期し、将来の経営方針に支障が出ないように配慮することが重要です。
アーリー期の資金調達
アーリー期の資金調達は、事業の拡大や売上の加速を目指して行われます。アーリー期は「プレシリーズA」「シリーズA」のラウンドに該当し、製品・サービスの市場投入に向けたマーケティング費や製造ラインの増強のほか、人材採用や設備投資といった資金が必要です。
アーリー期には、シード期よりも大規模な資金調達が求められます。調達手段としては、ベンチャーキャピタル(VC) からの出資をはじめ、クラウドファンディングや補助金を併用する方法などもみられます。
<アーリー期の資金調達概要>
| 項目 | 内容 |
|
ラウンドのフェーズ |
プレシリーズA、シリーズA |
|
資金調達方法 |
・ベンチャーキャピタル(VC) |
|
リスク・注意点 |
・経営に影響を与える出資条件が発生する可能性 |
アーリー期の資金調達では、普通株式とは異なる権利を持つ「優先株式」が発行される場合もあります。優先株式は、配当や残余財産の分配で優先権を持つため、投資家にとって魅力的であり、企業にとっても資金調達を容易にする手段です。優先株にはA種やB種といったアルファベットが付されることが多く「シリーズA」という名称もこれに由来しています。
また、アーリー期においては、PMF(プロダクトマーケットフィット)の実現やその見通しが重要です。PMFが達成されていないと、事業の成長性を示すことが難しく、期待する資金調達額に届かない可能性があります。
アーリー期の資金調達は、企業の成長を加速させる機会であると同時に、慎重な判断が必要です。特に、投資家との契約条件や返済計画を適切に管理しなければ、のちの事業運営に負担を与える可能性があります。投資家との信頼関係を築きながら、次の段階に備えた基盤づくりが必要です。
ミドル期の資金調達
ミドル期の資金調達は、企業が成長を本格化させるために重要な段階です。ミドル期は「シリーズB」のラウンドに該当し、単月黒字化やさらなる市場拡大、製品改良に向けた資金調達が行われます。
ミドル期の企業は、すでに一定の実績を持つため、大手企業やPEファンドからの出資や金融機関のプロパー融資も選択肢に入ります。より高額な資金調達が実現し、成長を支える体制が整います。
<ミドル期の資金調達概要>
| 項目 | 内容 |
|
ラウンドのフェーズ |
シリーズB |
|
資金調達方法 |
・ベンチャーキャピタル(VC) |
|
リスク・注意点 |
・資金調達に伴う株式分配と経営の自由度に注意 |
シリーズB以降では、事業の安定を前提に、さらに多額の資金が求められます。このため、ベンチャーキャピタル(VC)やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)に加え、事業会社との資本提携やプロパー融資など、多様な資金調達手段が選択肢に入ります。
特に「ベンチャーデット」は、将来の資金調達力や成長性に注目した負債性の資金調達方法です。新株予約権付き融資や社債発行が代表例で、企業の財務状況よりも成長ポテンシャルに基づいて融資判断が行われます。
また、ミドル期の資金調達には、顧客あたりの収益性を指す「ユニットエコノミクス(UE)」の達成が求められます。UEが成立すると、事業が拡大するほど利益が増える状態を示し、これによってシリーズA以前には難しかった資本提携やベンチャーデットなどの調達が可能になります。
シリーズBの資金調達は調達額が大きくなるため、投資家による資金提供の判断が一層慎重に行われます。この過程では、企業の財務状況やリスクを詳細に調査する「デューデリジェンス」が実施され、場合によっては半年以上を要することもあります。
なお、資金調達による株式の分配には、経営の自由度低下のリスクも伴います。特に、持株比率が低下しすぎると経営権の希薄化により意思決定に影響が及ぶため、分配には慎重な判断が必要となることを留意しておきましょう。
レイタ―期の資金調達
レイター期の資金調達は、企業が成長の最終段階において、IPO(株式上場)やM&A(事業売却)といった出口戦略を具体的に検討するために行われます。レイタ―期は「シリーズC」以降のラウンドに該当し、既存事業の安定に加え、新規事業や新市場への進出を見据えた多額の資金が必要です。
<レイタ―期の資金調達概要>
| 項目 | 内容 |
|
ラウンドのフェーズ |
シリーズC以降 |
|
資金調達方法 |
・金融機関からの融資 |
|
リスク・注意点 |
・出口戦略に合った資金調達の選択が必要 |
レイター期の企業は、既存事業を安定化させながら新規事業や関連事業の開発にも注力し、組織規模の拡大と管理体制の強化が求められます。人員の増加に対応するため、管理部門の整備や評価制度の導入によって組織全体の効率を高めます。こうした内部体制の強化は、IPOやM&Aといった出口戦略の基盤作りに直結します。
IPOを目指す企業にとっては、成長計画と透明性の高い経営体制を評価するVCやPEファンドからの支援が有効です。これにより、上場準備に向けた株式公開のプロセスが円滑に進み、事業拡大に有利な投資環境が整います。
一方で、M&Aを検討する企業は、売却先のニーズに合わせた柔軟な資金調達が必要です。特に株主が多すぎると意思決定が複雑化し、売却交渉に影響が及ぶ可能性があるため、株主構成にも配慮する必要があります。
レイター期での資金調達には半年以上の準備期間を要します。金融機関からの融資や補助金の申請には詳細な事業計画書や予算計画が求められ、審査や手続きに数カ月かかることもあります。資金調達の計画を事前に整え、タイミングを見極めた上で進めることがポイントです。
まとめ
資金調達におけるラウンドとは、スタートアップが成長や事業拡大のために資金を調達する際、自社の現在の成長フェーズを投資家に示す目安となる指標です。初期段階のラウンドでは、少額の資金を多方面から調達し、事業が成長するにつれて調達額の規模を拡大させていきます。
資金調達のラウンドにおけるシリーズAでは、顧客基盤の拡大と収益化が重要視され、シリーズB以降ではIPOやM&Aを見据えた大規模な資金調達が行われます。資金調達の期間は半年以上かかる傾向にあり、企業が資金調達を成功させるには、事業ステージに応じて重ねてきた実績と詳細な事業計画が必要です。
投資家は企業の成長段階に応じたリターンを見込んで資金提供を行っており、特に後期のラウンドではVCやPEファンドからの投資が増える傾向にあります。各ラウンドでは返済条件や経営への影響といったリスクもあるため、企業は慎重に資金計画を立て、株主構成や資金使途の透明性を保つことにより将来的な成長基盤を強化します。
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
資金調達の可能性を無料で診断
10,000件の資金調達実績を持つSolaboの専門家が、融資や補助金など、事業課題に合わせた資金調達方法を提案します。
10,000件の資金調達実績を持つSolaboの専門家が、融資や補助金など、事業課題に合わせた資金調達方法を提案します。
関連記事