
銀行融資の金利相場と利息の計算方法を解説

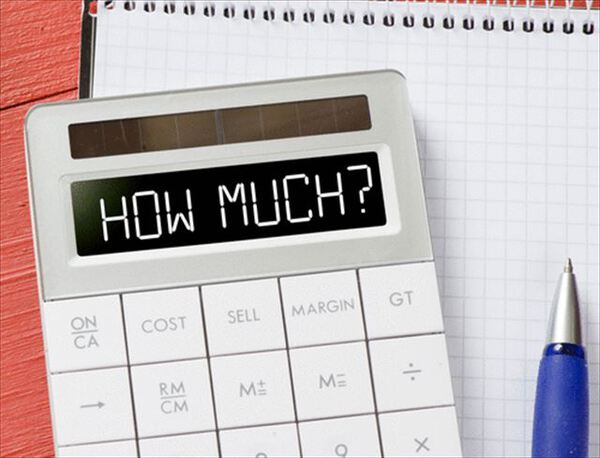
金利とは、資金の借り入れを行う際に借り手(債務者)が貸し手(債権者)に対して支払う利息の割合のことです。銀行融資によって資金調達を行う場合には、元金の返済に加えて設定されている金利に基づく利息を支払う必要があります。
当記事では、銀行融資の金利と利息について解説します。資金調達方法として銀行融資を検討しており、金利の相場や利息の計算方法を知りたいと考えている人は当記事を参考にしてみてください。
銀行融資の金利相場
銀行融資における金利の相場は、融資の種類によって異なる傾向にあります。実際に適用される金利は事業者の信用情報や返済期間、担保の有無などにより変動しますが、大まかな目安として銀行融資の種類ごとの金利相場を確認してみましょう。
<銀行融資の種類ごとの金利相場>
|
銀行融資の種類 |
概要 |
金利相場(年利) |
|
プロパー融資 |
銀行と利用者が直接取引を行う融資。信用力の高い事業者であれば低金利で借入が可能 |
1.0%~3.0% |
|
信用保証付き融資 |
信用保証協会が保証を行う融資。保証料が発生するもののプロパー融資よりも融資を受けやすくなる |
1.5%~3.0% ※加えて0.5〜2%程度の保証料がかかる |
|
ビジネスローン |
事業者向けのローン商品。無担保無保証人で利用できる制度があり、中小企業でも利用しやすい |
メガバンク:1.5%~14.0% 地方銀行:3.0%~15.0% |
|
ビジネスカードローン |
事業者向けのカードローン。限度額までであればATMなどから繰り返し現金を引き出せる |
3.0%~18.0% |
プロパー融資は、銀行と利用者が直接資金の取引を行う融資です。審査では事業者の信用情報や財務状況が重視されるため中小企業や実績の少ない企業は利用が困難となる傾向にありますが、金利相場は年利1%~3%程度であり保証料が必要ないことから、資金調達にかかるコストを抑えることができます。
信用保証付き融資は、信用保証協会が保証人となり銀行と利用者の取引をサポートする融資です。金利相場は年利1.5%〜3.0%程度であり、利息に加えて0.5〜2%程度の保証料が発生しますが、銀行側の貸し倒れリスクが軽減されることからプロパー融資と比較して審査に通りやすくなる傾向にあります。
ビジネスローンは、事業者向けのローン商品です。審査が比較的甘く通常の融資を断られてしまった場合でも利用できる可能性がありますが、金利はメガバンクで年利1.5%〜14.0%程度、地方銀行で年利3.0%〜15.0%程度とプロパー融資や信用保証付き融資よりも高く設定されている傾向にあります。
ビジネスカードローンは、事業者向けのカードローンであり、銀行やコンビニのATMを利用して現金を引き出せるため最短即日での資金調達が可能な方法です。他の融資商品と比較して審査が簡易である一方、金利が高く設定されている場合があるほか、限度額が低いことや借入期間が短いことがあります。
なお、融資における金利の上限は「利息制限法」によって定められています。融資の種類にかかわらず、借入元本が10万円未満の場合は年20.0%以下、10万円以上100万円未満の場合は年18.0%以下、100万円以上の場合は年15.0%以下と定められおり、上限を超える金利設定での融資は違法取引であることを念頭に置いておきましょう。
金利設定の種類
銀行融資の金利設定には「固定金利」「固定金利選択型」「変動金利」の3種類があります。金利設定によって最終的な利息の支払い額が大幅に変動する可能性があるため、銀行融資の利用時には固定金利、固定金利選択型、変動金利それぞれの特徴を確認しておきましょう。
<金利設定の種類>
|
金利設定の種類 |
概要 |
|
固定金利 |
|
|
固定金利選択型 |
|
|
変動金利 |
|
固定金利は、融資契約の期間中が一定に保たれる金利タイプです。借入時点での金利は変動金利よりも高く設定されている傾向にありますが、返済終了まで金利が変わらないため、長期間の借入において将来的な金利上昇に不安がある人や返済計画を明確にしておきたい人は固定金利が向いています。
固定金利選択型は、銀行や融資商品ごとに設定されている特約期間中の金利が固定される金利タイプです。特約期間の終了後に再度金利設定を選択できるため、固定金利と変動金利のどちらにするか迷っている人や、金利動向を見つつ状況に応じた選択をしたい人は固定金利選択型が向いています。
変動金利は、市場動向に合わせて利率の見直しが行われる金利タイプです。借入時の金利は固定金利よりも低く設定されている傾向にあるため、初期の金利をできる限り抑えたい人や、借入期間が短く金利変動の影響を受けにくいと判断する人は変動金利が向いています。
なお、金利設定は利用者が自由に選択できる場合もあれば、融資商品ごとに決められている場合もあります。事業者向けの銀行融資の場合、融資商品ごとに固定金利または変動金利が決められている傾向にあるため、利用する制度を選択する際の判断材料のひとつとしてみてください。
利息の計算方法
銀行融資における金利の相場や金利設定の種類を押さえた人は、利息の計算方法を確認してみましょう。銀行融資を受けた場合の利息の支払い金額は、以下の計算式によって求めることができます。
<利息の計算式>
|
元金×金利÷365※×借入日数 ※うるう年の場合は366で算出 |
銀行融資の金利は原則として年利で記されているため、まずは元金に年利を乗じて1年間に発生する利息の金額を算出します。つぎに、1年間の日数である365を除することによって1日当たりの利息を計算し、最後に借入期間を乗じることによって利息の総額を求めることができます。
たとえば、金利が3%の銀行融資を利用して、100万円の資金を30日間借り入れた場合の利息を求める場合の計算式は「100×0.03÷365×30≒2,465」であり、約2,465円の利息を支払うことになります。借入額が大きい場合や借り入れ日数が長い場合は、その分利息の支払い額も多くなります。
また、分割払いの場合は返済ごとに元金が減少していくため、返済時の借入残高をもとに計算をします。金利が3%の銀行融資を利用して100万円の資金を借り入れ、30日ごとに25万円ずつ返済する場合、1回目の返済時の利息は「100万×0.03÷365×30≒2,465」、2回目の返済時の利息は「75万×0.03÷365×30≒1,849」となり、返済を重ねるごとに1回あたりの利息の金額は減少します。
なお、さまざまな条件において利息がどれくらいかかるかを確認したい場合は、金融機関等のホームページで公開されている「返済シミュレーション」を活用することも可能です。あくまでも目安となりますが、自身の状況においてどれくらいの利息が発生するのかを知りたい人は参考にしてみてください。
返済方法による利息の支払い総額の違い
銀行融資の返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。どちらの返済方法を選択するかによって月々の返済額や利息の支払い総額が変わるため、年利3%、借入金額120万円、返済期間1年という条件で銀行融資を受けた場合における、それぞれの返済額を比較してみましょう。
<元利均等返済と元金均等返済における返済額の違い>
|
支払い回数 |
元利均等返済 |
元金均等返済 |
||||
|
支払額(円) |
元金(円) |
利息(円) |
支払額(円) |
元金(円) |
利息(円) |
|
|
1回目 |
101,632 |
98,632 |
3,000 |
103,000 |
100,000 |
3,000 |
|
2回目 |
101,632 |
98,879 |
2,753 |
102,750 |
100,000 |
2,750 |
|
3回目 |
101,632 |
99,126 |
2,506 |
102,500 |
100,000 |
2,500 |
|
4回目 |
101,632 |
99,374 |
2,258 |
102,250 |
100,000 |
2,250 |
|
5回目 |
101,632 |
99,623 |
2,009 |
102,000 |
100,000 |
2,000 |
|
6回目 |
101,632 |
99,872 |
1,760 |
101,750 |
100,000 |
1,750 |
|
7回目 |
101,632 |
100,121 |
1,511 |
101,500 |
100,000 |
1,500 |
|
8回目 |
101,632 |
100,372 |
1,260 |
101,250 |
100,000 |
1,250 |
|
9回目 |
101,632 |
100,622 |
1,010 |
101,000 |
100,000 |
1,000 |
|
10回目 |
101,632 |
100,874 |
758 |
100,750 |
100,000 |
750 |
|
11回目 |
101,632 |
101,126 |
506 |
100,500 |
100,000 |
500 |
|
12回目 |
101,632 |
101,379 |
253 |
100,250 |
100,000 |
250 |
|
合計 |
1,219,584 |
1,200,000 |
19,584 |
1,219,500 |
1,200,000 |
19,500 |
|
※年利3%、借入金額120万円、返済期間1年として算出 ※諸条件により実際の返済額とは異なる場合がある |
||||||
元利均等返済は、月々の返済額が一定となる返済方法です。月々の返済額が一定のため返済計画を立てやすいことや初期の返済額が少なくなるというメリットがある一方で、借入残高の減り方が元金均等返済よりも遅いため利息の総支払額は多くなることがデメリットとなります。
元金均等返済は、月々の返済額のうち元金の金額が一定となる返済方法です。返済が進むにつれて返済負担が減ることや利息の総支払額が少なくなるというメリットがある一方で、返済開始時の返済額が元利均等返済よりも高くなるため、審査において収入や財務状況がより厳しくチェックされる傾向にあります。
上記の例よりも金利が高い場合や借入金額が多い場合、返済期間が長い場合などは、元利均等返済と元金均等返済による利息の支払い総額の差はさらに大きくなります。元利均等返済と元金均等返済にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、自身の状況に合わせて返済方法を選択しましょう。
支払い回数による利息の支払い総額の違い
銀行融資を受けた場合、金利や借入金額、借入期間が同じであっても、設定する支払回数によって利息の支払い総額が変わります。年利3%、借入金額120万円、返済期間1年という条件で銀行融資を受けた場合における、支払い回数ごとの利息の総額を比較してみましょう。
<支払い回数による利息の支払い総額の違い>
|
支払い回数 |
利息の総額(円) |
|
年1回(一括払い) |
36,000 |
|
年2回 |
27,000 |
|
年4回 |
22,500 |
|
年6回 |
21,000 |
|
年12回(毎月払い) |
19,500 |
|
※元金均等返済の場合 ※年利3%、借入金額120万円、返済期間1年として算出 ※諸条件により実際の返済額とは異なる場合がある |
|
銀行融資を受けた場合の利息の金額は、借入残高をもとに算出されます。返済を重ねるごとに借入残高が減ることで利息の金額も低くなっていくため、完済までの期間が同じであれば支払い回数が多い方が利息の支払い総額は少なくなります。
ただし、銀行振込による返済を行う場合は振込手数料が発生する場合があります。振込手数料は原則として債務者である融資の利用者が負担することになるため、返済方法によっては支払い回数分の振込手数料が発生する可能性があることにも留意しておきましょう。
利息の負担を軽減するためのポイント
銀行融資の利用を検討している人は、利息の負担を軽減するためのポイントを押さえておきましょう。銀行融資を利用した場合には原則として利息の支払いが発生することになりますが、工夫次第で適用される金利を抑えて利息の負担を軽減できる可能性があります。
<利息の負担を低減するためのポイント>
- 返済期間を短く設定する
- 複数の制度を比較して金利の低い融資制度を利用する
- 担保を用意する
- 自己資金を用意する
- 信用情報を健全に保つ
たとえば、金利を抑えるためのポイントとして「返済期間を短く設定すること」が挙げられます。利息は借入日数に応じて増えるため返済期間を短くすれば利息が発生する日数を減らせるほか、長期の借入よりも短期の借入の方が低い金利が適用される傾向にあります。
また、金利を抑えるためのポイントとして「複数の制度を比較して金利の低い融資制度を利用すること」が挙げられます。金融機関や融資商品によって適用される金利は異なり、同じ条件でも低金利で借入ができる場合があるため、複数の制度を比較したうえで金利の低いものを選ぶことも有効です。
さらに、「担保を用意すること」「自己資金を用意すること」「信用情報を健全に保つこと」は資金の返済能力を示すことにつながります。銀行融資を受ける際に、銀行側から貸し倒れのリスクが少ないと判断されることにより、適用される金利を下げられる可能性があります。
なお、信用力が高い優良企業であると判断された場合には、最優遇貸出金利である「プライムレート」が適用されることがあります。プライムレートの適用の有無は金融機関の審査によりますが、1%以下の低金利で借入ができる可能性もあるため、銀行融資を利用したいと考えている人は予備知識として覚えておきましょう。
まとめ
金利とは、資金の借り入れを行う際に借り手が貸し手に対して支払う利息の割合のことです。銀行融資を利用して資金調達を行う場合には、元金の返済に加えて適用された金利に基づく利息を支払う必要があります。
銀行融資における金利の相場は、融資の種類によって異なる傾向にあります。適用される金利はさまざまな要因によって変動しますが、プロパー融資や信用保証付き融資は金利が低く審査が厳しい傾向にあり、ビジネスローンやカードローンは金利が高く審査が甘い傾向にあります。
また、金利に基づく利息は「元金×金利÷365×借入日数」の計算式で求めることができます。借入金額や返済期間が同じであっても、返済方法や返済回数の選択によって利息の支払い総額が変わるため、融資の利用を検討している人は返済シミュレーションなどを用いて利息の目安を把握しておきましょう。
なお、工夫次第で利息の負担を軽減できる可能性があります。返済期間の設定や担保の提供などにより、銀行側から貸し倒れのリスクが少ないと判断されれば適用される金利を下げられる可能性があるため、銀行融資の利用を検討している人は利息の負担を抑えるためのポイントを確認しておきましょう。
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
資金調達の可能性を無料で診断
10,000件の資金調達実績を持つSolaboの専門家が、融資や補助金など、事業課題に合わせた資金調達方法を提案します。
10,000件の資金調達実績を持つSolaboの専門家が、融資や補助金など、事業課題に合わせた資金調達方法を提案します。





