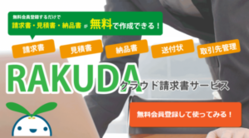給料を支払う際には注意!意外と知らない、給与支払における5つのルールとは?


消費税が8%に上がり、サラリーマンにとって懐やや寒し…ですが、
給与を”支給している側”にとっても、消費税増税のなかで、なんとか日々の経営をやりくりしていることでしょう。
実際、経営者にとっては、給与をもらう立場の人以上に懐が厳しい今日この頃・・・なのかもしれませんね・・・。
さてそんな経営者の方にとって、給与を支給する際に注意すべき点がいくつかあります。
今回は意外と知られていない「賃金の支払い5原則」についてお話しします。
労働基準法11条では「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義しています。
ですので毎月支払う給料のほか、賞与や退職金なども、賃金となります。
また、労働基準法24条1-2項では給料の支払いについて、下記のように定めています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」
分かりやすく見ていきましょう。
賃金の支払い5原則
1.まず、給料は通貨、つまり「現金」で支払うのが原則であり、小切手やモノなどの現物で支払うことは原則として許されていません。
但し社員の同意を得た場合は、銀行に振込むことも可能です。
2.また、給料は従業員本人に対して支払わなければならず、代理人に支払うことは違法となります。
但し”従業員の使者”として、妻や子が従業員本人の印鑑を持参し、本人名義で受領することは差支えありません。
なお、ここでいう「使者」とは家族などが妥当とされています。
会社の同僚ではダメだという事ですね。
3.給料は原則として全額を、社員本人に支払わなければなりません。
但し所得税や社会保険料等の「法的に定められたもの」については、会社に源泉徴収義務があるので、控除すべきとされています。
また、別途労使協定を結んでいる場合は、社宅家賃・親睦会費なとを賃金から控除して支払うことができます。
4.給料は毎月1回以上、支払わなければなりません。
どんなに額が小さくても、ひと月に1回以上は賃金を支払わなければならないことになっています。
但し賞与や退職金については、このルールは適用しません。
それでは、年俸契約の場合はどうなのでしょうか?
年俸制とは、年間の額の決め方だけなので、年俸制による賃金の場合であったとしても、毎月1回以上払いの原則は適用されます。
5.給料は毎月、「一定の期日に」支払わなければいけません。
一定期日とは、例えば給与の支払日を毎月10日、25日などと特定することを指します。
会社の資金繰り的な都合で、今月は25日払い、来月は30日払い…
などと勝手に支払日を変更することは許されません。
但し本人や家族に災害、疾病等があったり、急に費用が必要になったような場合は、この限りではありません。
まとめ
如何でしたでしょうか?
ついうっかりやってしまいそうなことも、禁止事項として定められているように思いますね。
労働基準法24条に書かれていることは上記1.~5.に纏められるので、
俗に「賃金の支払い5原則」と呼ばれたりします。
給与の支給の仕方も、ちゃんと法律で定められているのですね…。
請求書・見積書・納品書を簡単便利に作成できる「RAKUDA」
無料で「請求書」「見積書」「納品書」「送付状」「取引管理」が作成できるクラウド請求書ツールです。
請求業務がコレで完結。
面倒な源泉徴収税の計算も自動で行ってくれます。
個人事業主の方には特におススメ!
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
月額20,000円からの記帳・経理代行
会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。
会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。