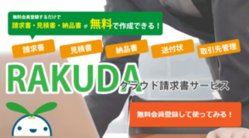個人事業主に必要な「必要経費」についての考え方


独立して個人事業主になると、サラリーマンとどこが違うのか?
最も大きな違いとして、税金を自分で計算しなければいけない点が挙げられます。
個人事業主の所得税は、1年間(1月~12月)の総売上から必要経費を差し引いた課税対象額に対して、税率を掛けて計算されます。
年間総売上-必要経費=利益(=事業所得)
もちろん、税金はしっかり払わなければいけません。しかし、余計な税金は払いたくないものです。
そこで、経費を漏れなく計上することが大切です。
では、必要経費とは何か?
サラリーマン時代にはあまりピンとこなかった方もいらっしゃるかもしれません。
経費といっても、支出という支出はなんでも経費になるわけではありません。
どこまで経費として認められるのかを、きちんと把握しておきましょう。
簡単にいうと必要経費とは「仕事を行うために必要な費用」を指します。
どこまでが必要経費になるの?
仕事に必要な経費と言うと、どのようなものが思い浮かぶでしょうか?
- 文房具、コピー用紙、パソコン用品等の消耗品費
- パソコンや周辺機器、パソコンソフト代
- 営業、打ち合わせ等での交通費
- 家賃、光熱費、通信費等の事務所経費
主な経費といえば、ざっと考えただけでも上記が挙げられます。
それでは、主な経費を見ていきます。
什器備品、消耗品
仕事に必要な機材や消耗品は、すべて経費として認められます。
パソコンや周辺機器、パソコンソフト、文房具、コピー用紙、仕事机や椅子、本棚等が挙げられます。
10万円未満の物品は、全額が一括経費となります。しかし、10万円以上になると、一定の場合を除き資産として扱われます。耐用年数により、1年分の減価償却費が経費となります。機材や備品の修理費、保守契約料も経費となります。
消耗品費
・10万円未満の什器備品
・文房具、パソコン用品、その他の消耗品
減価償却費
・10万円以上の什器備品(1年の減価償却分が経費となる)
修繕費
・パソコン等機材の修理代
・保守契約料
事務所経費
フリーの個人事業主の場合、とりあえず自宅を事務所にする場合が多いですね。
こうした場合、家賃はどこまで経費になるでしょうか?
このように、プライベートの生活で使う部分と、仕事として使う部分とを、明確に分けるのが難しい経費を「家事関連費」と呼びます。
家事関連費は、仕事で使う割合を計算(経理では「按分する」といいます)して、業務割合分が経費として認められるようになっています。
毎月支払っている家賃のうち、どれだけ経費になるのでしょう?
それは、仕事部屋の占有面積によって割合を算出することになっています。また、住宅ローンを支払っている自宅を事務所にした場合は、ローンの利息のみが経費の対象となり、事業割合分を経費として算出します。火災保険も同様に、事業割合が経費と認められます。
家賃
・家賃、家賃の更新料
・火災保険料
・住宅ローンの支払利息
(それぞれ専有率で按分します)
水道光熱費
・電気代、ガス代、水道代
・灯油代
(それぞれ使用率で按分します)
通信費
・電話料、携帯電話料
・インターネット接続費
(それぞれ使用率で按分します)
1ヵ月の賃貸料×使用面積の割合(仕事場の面積÷全体の面積)
※一般的には面積で計算します。「業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合」、税務署に必要経費として認めてもらえることから、仕事専用の部屋を用意することをおすすめします。
※水道光熱費や通信費も、仕事に使う割合を算定します。比率は自分の判断で決めて構いません。判断基準は、実態に即しているかどうかです。税務署で聞かれた時に、妥当と判断されれば、問題はありません。
例えば、携帯電話をプライベート用と仕事用に分けて持てば、仕事用の携帯電話代は全額経費にできます。
自動車の経費
「家事関連費」の中には、自家用車の経費も該当します。
自動車を仕事でしか使わなければ、その経費は全額、必要経費となります。自宅兼事務所の場合と同様に、自家用車を仕事にも使用する場合は、費用の内、使用割合に応じた分が経費として認められます。車の購入費の減価償却費も、業務使用分が経費となります。
車の経費
・ガソリン代
・駐車場代
・修理費
・自動車税、自動車保険料
・車の購入費の減価償却費
(それぞれ使用率で按分します)
※業務使用中の高速料金、駐車料金は全額経費になります
ガソリン代等:ガソリン代等×使用割合
減価償却費:車の減価償却費×使用割合
※使用割合=週または月のうち何日仕事に使用するか
情報収集や資料代
仕事をする上で必要な情報や資料代、技能・知識・ノウハウを得るためのセミナー受講料等も必要経費として認められます。
ただし、資格取得の経費は「一身専属性(資格は個人に帰属する)」のものとなるため、経費になる、ならないの判断が解釈により異なる場合があります。納税地の税務署への確認が必要です。
主に以下の費用が想定されます。
- 各種資料代
- 新聞や雑誌の定期講読料(業務に必要な専門誌等)
- 雑誌、書籍代
- セミナー受講料(業務に直接必要であることが前提)
- 通信教育費(業務に直接必要であることが前提)
交通費
営業で外出した際の電車賃や、打ち合わせに出たときの電車賃等、買い物に出掛けたときの交通費等も経費になります。
電車、バス等の交通費は、基本的に領収書がありません。日ごろから記録しておく習慣をつけておきましょう。
打ち合わせの飲食代
取引先の担当者や仕事仲間と、仕事の打ち合わせをしながら居酒屋で飲食した。
これも立派な業務上の経費です。ワリカンにした場合でも、きちんと領収書をもらってきましょう。領収書には、打ち合わせ相手の名前と、要件をメモ書きしておきます。費用は「接待交際費」となります。
あるいは以下のようなケースが出てくることでしょう。
・喫茶店で企画案を考えた
・ランチをしながら仕事の打ち合わせをした
このような場合の飲食代も経費になります。この場合には、「打合会議費」という科目で処理します。
接待交際費
・取引先担当者やスタッフとの飲食代
・取引先へのお中元・お歳暮等の贈答品代
・仕事上の付き合いによる冠婚葬祭の包金
会議費
・打ち合わせに使った喫茶代
経費を漏れなく計上することが、正しい税金を納める第一歩。日ごろから領収書をもらうことを忘れないようにしましょう。
必要経費にならないもの
以下の費用は、必要経費にならないので注意しましょう。
- 所得税、住民税
- 健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります)
- 借入金の返済金(※利子は経費となります)
- 罰金(駐車違反の罰金等)
事業税は経費になりますが、所得税や住民税は経費になりません。
「今年は利益が出たから借金を返済しよう」と思っても、返済金額は経費とならず、利益から差引くことはできません。経費になるのは、利子だけです。
※同居及び生計を一つにする親族からの借入金に対する利子は、経費にはなりません。
主な必要経費にはどんな費用があるか、どこまで認められるか、アウトラインを把握いただけましたか。
さらに「青色申告」にするとこんな特典が
なお、所得税の申告方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告のメリット
白色申告は以下のメリットが挙げられます。
- 簡便な方法による記帳が認められており経理処理に時間をかけなくて済む
- 届出がいらない
※2014年1月から白色申告も記帳が義務化されました
※「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」
売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。
青色申告のメリット
一方、青色申告にすると、日々の経理業務において、複式簿記でしっかりと帳簿をつけることが義務づけられています。白色申告より手間がかかりますが、さまざまなメリットがあります。つまり、税金が安くなる優遇措置がいろいろとあるのです。
主なメリットは以下の通りです。
- 必要経費以外に最高65万円の控除が受けられる
- 赤字が出たらその損失分を繰り越せる
- 家族への給料が必要経費にできる(「青色専従者給与に関する届出書」の提出が必要)
- 貸倒引当金を、経費に繰り入れることができる
- 減価償却資産の特別償却など、特例措置を受けられる
これから事業を大きく成長させたいと考えている個人事業主の方には、ぜひ青色申告をおすすめします。
青色申告にすると、申告内容が税務署にスムーズに通りやすくなるといわれています。また、日々の仕事を計数管理することで、実際に儲けが出ているのか、事業として成立しているのかどうかを知ることができ、事業主としての自覚が芽生えます。
青色申告をするには手続きが必要
「節税できるなら、青色申告にしたい」
と思って青色申告をするには、手続きが必要です。
最寄りの税務署へ行って「所得税の青色申告承認申請書」の用紙をもらいましょう。必要事項を記入して提出すれば完了です。
ただし、以下のような提出期限があるのでご注意ください。(2013年度の申告の場合)
・2013年1月1日~1月15日までに開業→2013年3月15日まで
・2013年1月16日以降に開業→開業日から2ヵ月以内
届出は忘れずにしっかり手続きを行いましょう。
請求書・見積書・納品書を簡単便利に作成できる「RAKUDA」
無料で「請求書」「見積書」「納品書」「送付状」「取引管理」が作成できるクラウド請求書ツールです。
請求業務がコレで完結。
面倒な源泉徴収税の計算も自動で行ってくれます。
個人事業主の方には特におススメ!
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
月額20,000円からの記帳・経理代行
会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。
会計処理に関するご相談受付中!法税務申告や日々の経理業務など、企業の会計実務をサポートいたします。