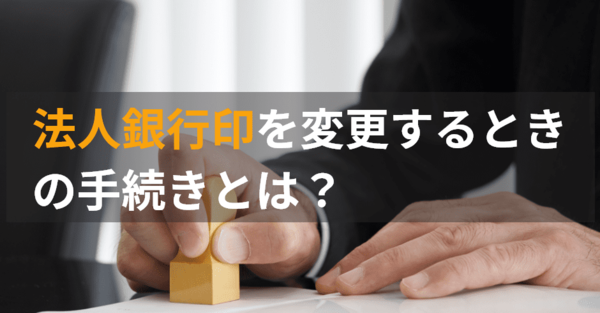会社設立にかかる費用を登記申請から段階別に解説

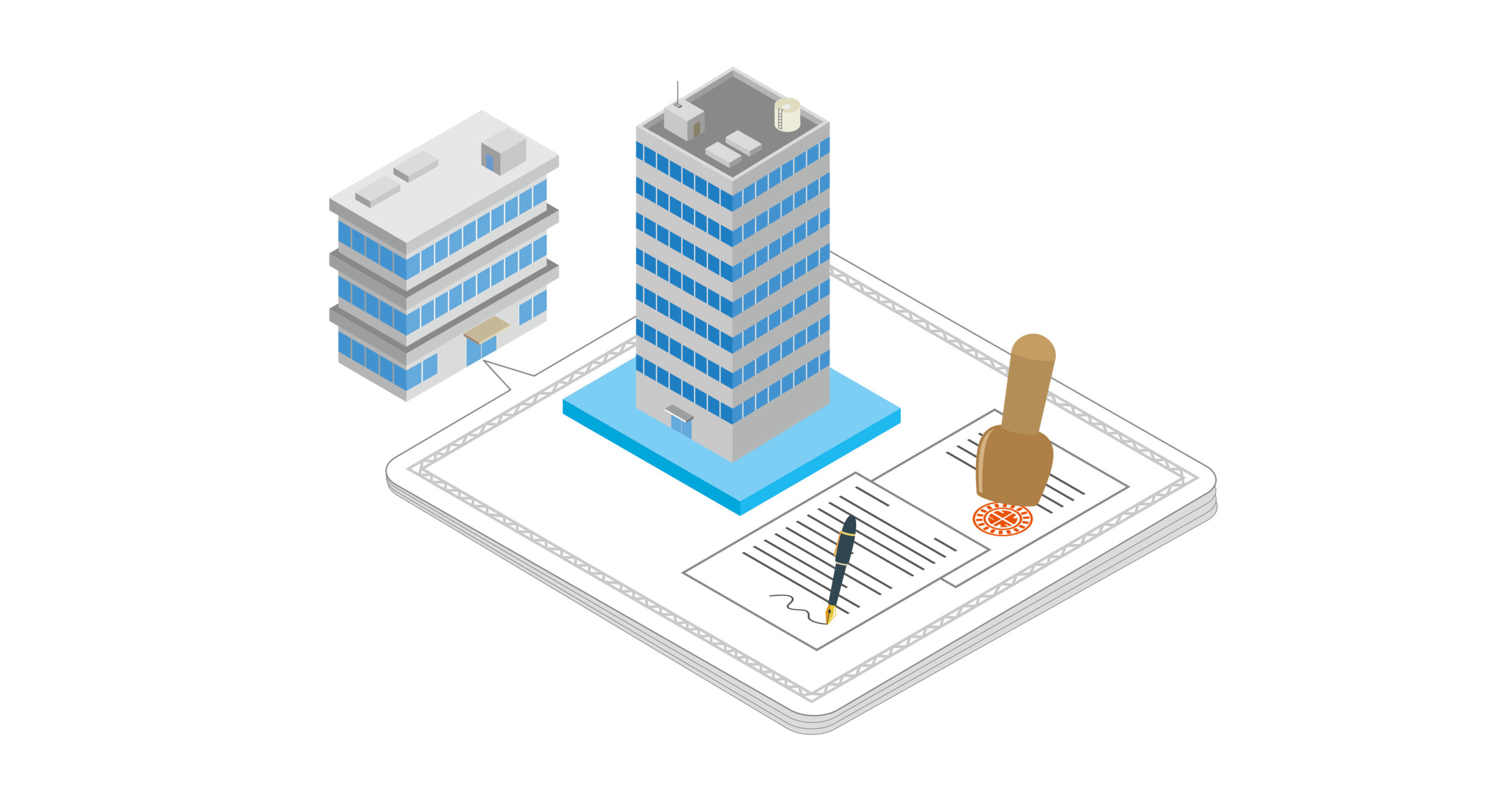
会社を設立する際は、登記申請から事業開始までの間に費用が発生します。費用は設立する会社の種類や業種によっても異なるため、会社設立を考えている人は、自身が会社設立する際にかかる費用相場を把握しておきましょう。
当記事では、会社設立にかかる費用を手続きの段階別に解説します。会社設立の際、どのタイミングでどのような費用が発生するのか知りたい人は参考にしてみてください。
会社設立の登記申請にかかる費用
会社設立の際には、法人として認めてもらうための登記申請が必要です。登記申請では、各種手続きや必要書類の発行にかかる手数料などの費用が発生します。
【登記申請や提出物の準備にかかる費用相場】※資本金を除く
|
支払先 |
必要書類や手続き |
株式会社 |
合同会社 |
|
公証役場 |
定款認証手数料 |
資本金100万円未満:3万円 資本金100万円以上300万円未満:4万円 その他:5万円 |
0円 ※定款認証手続きは不要 |
|
定款用収入印紙代 |
4万円 ※電子定款の場合は0円 |
4万円 ※電子定款の場合は0円 |
|
|
定款謄本手数料 |
1枚:250円 250円 ×(定款のページ数 + 認定書) ※おおむね8枚2,000円程度 |
0円 ※定款認証手続きは不要 |
|
|
法務局 (登記申請時) |
登記事項証明書(謄抄本) |
書面請求1通:600円 オンライン請求・送付1通:500円 オンライン請求・窓口交付1通:480円 |
書面請求1通:600円 オンライン請求・送付1通:500円 オンライン請求・窓口交付1通:480円 |
|
登録免許税 |
資本金額×0.7%または15万円のどちらか高い方 |
資本金額×0.7%または6万円のどちらか高い方 |
|
|
印鑑証明書 |
書面請求1通:450円 オンライン請求・送付1通:410円 オンライン請求・窓口交付1通:390円 |
書面請求1通:450円 オンライン請求・送付1通:410円 オンライン請求・窓口交付1通:390円 |
|
|
市役所 |
就任承諾書に押印した代表者個人の印鑑証明書 |
1通:300円 |
1通:300円 |
|
合計 |
約20万円 |
約10万円 |
|
参考:「主な登記手数料一覧」|法務局公式サイトおよび「会社の定款手数料の改定」|日本公証人連合会公式サイト
登記申請の際は、株式会社であれば登録免許税の納付や印鑑証明書などの発行で15万円以上の費用がかかる場合があります。また、登記申請に必要な書類には定款や資本金の払込証明書など、登記申請前に手数料や資本金の払込も求められるため、前もって十分な資金の確保が必要です。
登記事項証明書は登記登録後、税務関係の届出や法人名義の銀行口座を開設する際に必要です。また、印鑑証明書も登記登録後の不動産の賃貸借契約や融資、生命保険の保険金の請求時などに必要な書類です。いずれも、1通300〜600円程度で発行できます。
なお、登記申請の際にはさまざまな書類を準備する必要があります。登記申請の必要書類を詳しく知りたい人は「会社設立時の登記申請に必要な書類を解説」を参考にしてみてください。
専門家に頼んだ場合の登記申請の費用
登記申請手続きを専門家である士業に書類の作成や手続きの代行依頼したときは、専門家への手数料が発生します。依頼先によって料金やサポート範囲が異なる場合があるため、専門家に依頼する際は事務所の公式サイトで料金を確認後、比較して検討しましょう。
【司法書士に依頼した場合の費用相場】
|
費用の種類 |
株式会社 |
合同会社 |
|
登記申請手続きにかかる費用 |
約20万円 |
約10万円 |
|
司法書士への報酬(手数料) |
約10万円 |
約6~10万円 |
司法書士に登記申請手続きを依頼したときの報酬は、約10万円前後となる傾向にあります。合同会社を設立する際の報酬は、株式会社を設立する際の報酬より相場が安く設定されています。
なお、登記申請手続きは司法書士の独占業務であるため、登記申請書の作成と手続きのサポートを依頼できるのは司法書士のみであることに注意しましょう。税理士や行政書士に頼んだ場合、登記申請手続きは提携している司法書士に委託することになります。
登記申請後から税務や保険関係の届出にかかる費用
登記申請後には、税務や保険関係の届出の準備など事業開始のために必要な作業を行います。税務や保険関係の届出の作成や提出を自分で行う場合、費用は掛かりません。
【税務や保険関係の届出にかかる費用】
|
届出 |
費用相場 |
|
許認可申請 |
約20万円〜100万円(業種によって異なる) |
|
保険関係の届出 |
※自分で書類を作成、提出する場合は費用はかからない |
|
税務関係の届出 |
※自分で書類を作成、提出する場合は費用はかからない |
許認可申請の内容や費用は、業種によって異なります。たとえば食品営業許可の場合、飲食店営業は16,000円、自動販売機による食品の調理販売業は9,600円と、食品営業の中でも金額が細かく分かれています。
また、建設業許可は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類あり、それぞれ申請にかかる費用が異なります。複数の都道府県に営業所を設ける事業者の場合、どちらか一方のみの申請には登録免許税15万円、両方同時の申請には30万円と、食品営業許可に比べて高い金額となっています。
専門家に頼んだ場合にかかる税務や保険関係の届出の費用
税務や保険関係の届出の手続きは、専門家に代行してもらうことも可能です。手続きの内容によって依頼できる専門家が異なるほか、それぞれ報酬の相場も異なります。
【専門家に頼んだ場合に税務や保険関係の届出にかかる費用】
|
専門家 |
依頼できる手続き |
報酬相場 |
|
行政書士 |
許認可申請手続き |
4万円~20万円前後 ※業種によって異なる |
|
税理士 |
税務関係の届出 |
届出1件あたり数千円程度 |
|
社会保険労務士 |
保険関係の届出 |
数万円~10万円前後 ※保険加入の人数によって異なる |
許認可申請は行政書士の独占業務であるため、行政書士以外の士業には依頼できません。他の業務も、保険関係は社会保険労務士、税務関係は税理士と依頼できる業務が士業によって異なります。
それぞれ届出や手続きごとに、料金が単体で設定されています。たとえば、税理士の場合が法定調書の届出は5,000円、決算および申告書の作成は15万円などです。
なお、士業と顧問契約をしているときは、顧問料のみが発生し届出や書類作成のサポート費用がかからない場合があります。同じ士業でも依頼先によって費用の詳細は異なるため、依頼をするときは複数の事務所を比較検討しましょう。
税務や保険関係の届出後から事業開始までにかかる費用
事業開始までには、会計ソフトの導入や事業で必要な設備などの準備が必要です。自宅で起業するのか、オフィスを借りるかなどでも事業開始にかかる必要経費は人によって異なります。
【事業開始までにかかる費用相場】
| 項目 |
費用相場 |
|
会計ソフトの導入 |
一番安いプランで月約3,000~約4,000円 ※クラウド会計ソフトの場合 |
|
ドメイン作成 |
1~約6,000円程度 ※ドメインの種類やサービスサイトで大きく異なる |
|
オフィスの準備 |
月々約10,000~約50,000(賃貸) ※東京都内の場合 |
|
設備など備品および消耗品費 |
数万円~数十万円 |
|
維持費(家賃、水道光熱費など) |
月々数万円~数十万円 |
たとえば、会計ソフトの場合、クラウド会計ソフトであれば月約3,000~4,000円程度で利用が可能です。他にも、事業内容によって必要となるシステムや設備などがある場合は、購入費や導入研修などさまざまな費用が発生します。
なお、会社設立にかかった費用は経費として処理することで純利益を減額できるため、税負担の軽減につながります。事業を始める際は必要経費を洗い出し、決算に向けて費用の記録を残しておきましょう。
専門家に頼んだ場合にかかる事業開始までの費用
会社設立の届出を出した後、経営相談や会計管理などの相談を専門家にすることになるでしょう。専門家に相談する際は、単発で一時的に相談する方法と、毎月の顧問料を払って相談する方法があります。
【各士業の料金相場】※企業規模によって異なる
|
専門家 |
顧問料の相場(月額) |
|
税理士 |
約1~5万円程度 |
|
中小企業コンサルタント |
約20~50万円程度 |
|
行政書士 |
約1~15万程度 |
会計ソフトを導入する際は、顧問税理士にサポートを依頼することもできます。費用相場は月約15,000~50,000円程度ですが、顧問料に記帳代行の料金を含んでいたり単発の業務としていたりと、サポート範囲や料金体系は事務所によって異なります。
中小企業コンサルタントの場合、料金体系は「プロジェクト型」「成功報酬型」「時間契約型」「顧問契約型(アドバイザリー契約)」の4種類あります。顧問契約型は月に数回会社を訪問して経営者の相談に応じるサポート方法であり、費用相場は約20~50万円程度ですが、事業者の企業規模や従業員数ごとに料金が異なる場合があります。
行政書士は業務ごとに料金設定されている場合が多く、月額約1~15万程度です。また、個人事業主と法人の場合でも料金設定が異なる場合があり、法人の方が個人事業主よりも高く設定されている傾向にあります。
士業の顧問料は、事務所や依頼する側の企業規模などで料金が異なります。会社設立にかかわる業務の相談や代行を依頼する際は、自社にあった専門家へ業務を依頼しましょう。
まとめ
会社設立の登記申請をするためには、各種手続きや必要書類をそろえるために費用がかかります。株式会社の場合、定款認証や登録免許税などの費用として15万円以上が必要となる場合もあります。
税務や保険関係の届出の書類作成や手続きを専門家に代行する場合も、それぞれ単発業務なら数千円~数万円の手数料が発生します。ただし、事務所ごとに料金体系が異なるため、依頼する際はそれぞれの公式サイトを確認して料金比較を行いましょう。
なお、事業開始までの間にも、設備導入やオフィス利用料などの費用がかかります。会社設立にかかった費用は経費として処理することで税負担の軽減につながるため、事業を始める際は必要経費を洗い出し、決算に向けて費用の記録を残しておきましょう。
この記事を書いたライター

ソラボ編集部
会社設立のご相談はこちら
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。
会社設立に関するご相談受付中!法人設立の手続きから必要書類まで、丁寧にサポートいたします。
関連記事